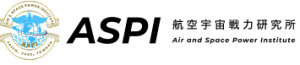司令官メッセージのシリーズその7:「航空総隊は、品質管理の進化と品質文化の成熟・伝承に努めよう」
「司令官メッセージ」という伝達形式で、当時隷下部隊による任務完遂に対する称賛を目的にして発した第7弾になります。
「航空総隊は、品質管理の進化と品質文化の成熟・伝承に努めよう」:平成28年11月17日
空自における品質管理の歴史は古く長い。創設当時から防衛省の品質管理部門をリードしてきたと言えるでしょう。
品質管理概念の導入当初は、米軍規格に準ずるケースが多かったようですが、昭和50年代後半以降、防衛庁の独自規格や国際規格を使用する体制を次第に整えていきました。平成の時代に移り、我が国の安全保障環境の変化に伴い、国際貢献任務を果たす機会が増え、過酷な状況下でも隊員の旺盛な改善意欲を持って、適切な品質管理を維持してきました。平成15年~20年の間に実施したクウエート派遣任務の実績こそが、その証の最たるものです。
しかし、航空総隊(以下「総隊」)における最近3か年度の人的過誤による事故は、
件数の増加もさることながら、それらの発生内容から品質管理への取り組みに対する不備が生起し、大事故の誘因となりかねないと考えます。
同時期の服務規律違反件数が増えていることも考え合わせると、組織における精強性と健全性の両輪に綻びが生じつつあると言わざるを得ません。
F35Aの導入に代表されるように、従来と大幅に異なる各種概念、要領、手続き等を取り込み、総隊が独自の品質文化を高みに練りあげていくために相当な努力が必要とされる時期に、先の現状はあるべき姿に逆行し、負のスパイラルに突入していくのではないかとの危機感を持っています。
品質文化を形成するには、先達がこれまで築き上げてきた教育訓練体制を活用し、プロフェッショナルな人材を育成することと、航空装備品によっては関係会社の高度な知識と技術に基づく支援態勢を確保することが重要です。特に、隊員に求める資質としては、任務遂行に対する意欲と不具合などに対する探究心や創造力が旺盛であることがポイントになります。
現在、総隊はQCサークル活動に積極的に取り組んでいます。今年度からは、さらなる業務改善意欲と技量の両面における向上をめざし、QCサークル・サミットと称し、部隊の現場で同活動を牽引し、全国レベルで輝かしい成果をあげている准曹士を横田基地において一堂に会した集合訓練に着手しました。近い将来において、その成果が活かされることを期待しているところです。ぜひ、空自の品質文化を総隊から発展・成熟させていきましょう。
司令官メッセージのシリーズその6:「伊勢志摩サミット支援任務を完遂した全部隊等を称賛!」
「司令官メッセージ」という伝達形式で、当時隷下部隊による任務完遂に対する称賛を目的にして発した第6弾になります。
「伊勢志摩サミット支援任務を完遂した全部隊等を称賛!」:平成28年5月28日
北海道洞爺湖サミット以来、8年ぶりに日本において開催された伊勢志摩サミットは、不測の事態に見舞われることなく、予定どおりの日程を終え閉幕。参加国の要人等は、すでに帰国の途につかれている。
当該サミットにおいては、世界経済の堅調化のための政策協調が主体であったものの、我々の基本任務にかかわる北朝鮮の非核化、海上安全保障、テロ対策等、安全保障上の議題についても、各々に合意形成が図られ、我が国政府として一定の成果が得られたものと思料する。
航空総隊によるサミット期間中の諸支援活動を総括してみると、一部装備品等の不具合が生じたが、代替手段を講じ任務遂行に影響を及ぼすことなく、整斉と実施することができた。今次のサミットでは、過去最大となる警察官の動員数と報道されていたことから、様々な事案・事態が発生する可能性は決して低くはなかった。総隊としても、こうした予断を許さない状況、並びに変化する航空気象に適応し、空自組織が有する本領の発揮に努めたところである。
世界の主要国等が注目した国家イベントに関われたことは、まさに誇りである。また期間中、些細な事故も発生させず、人的・物的戦力の低下を生じさせなかったことは、各人が自らを強く律した結果だと確信している。
かかるように、総隊が今次のサミット支援活動をほぼ計画どおり実施し得たのは、航空支援集団、航空教育集団、補給本部等、空自の関係部隊はもとより、他省庁、関係自治体、陸海関係部隊等との密接な連携による賜物と関係各位に深く感謝する次第である。
結びにあたり、伊勢志摩サミットの支援活動を通じて得られた教訓等を決して散逸させることなく、2020年開催の東京オリンピック等をはじめとする将来の国家的行事における安全確保の資として、後進に継承されんことを切に要望したい。
司令官メッセージのシリーズその5:「伊勢志摩サミットにかかわる支援活動は、作戦意識のもとに!」
「司令官メッセージ」という伝達形式で、当時隷下部隊に任務意欲の高揚を目的に発信していた、第5弾です。安全保障の観点から国家行事を無事に終了させるために、あらためて任務遂行上の心構え等について、メッセージを発したものです。
なお、同サミットが終了した直後のメッセージはのちほど掲載します。
「伊勢志摩サミットにかかわる支援活動は、作戦意識のもとに!」:平成28年4月25日
伊勢志摩サミット開催までのカウントダウンが刻まれている中、『世界の難題 協調練る』『対テロ、核軍縮を議論』『経済失速回避へ結東』等と、 広島市で行われた先の外相会合を皮切りにサミット関連報道が頻繁化してきたところ。また、警察による警戒警備にかかる訓練が本格化するとともに、防衛省自衛隊においても、関連部隊等が統幕計画に基づき細部実施要領の検証を兼ねた事前訓練等を実施しているのは、承知のとおり。
サミット支援は、国家行事への貢献という大義や名誉のもとでの活動ではあるが、想定外の状況や緊急の事態が生起する可能性がわずかでもあるかぎり、サミット関連活動は有事対応の延長上で捉え、実行しなければな、ー らない。まさに「作戦」に匹敵する実任務を付与されたという認識を持つべきである。
この「作戦」を全うするために、航空総隊は年初から各種の見積り、検討、調整、計画及び事前訓練等、諸準備を周到に行い、対応能力の向上を着実に図り、かなりの実力と自信を得たものと確信している。開催まで1か月となった、この期に及んでは各人が「作戦」の完遂を強く意識することこそが肝要である。
私自身、この「作戦」に臨むにあたり、掌握と即断の2つのキー・ワードを念頭に置いている。他省庁、陸海部隊及び空自内他メジャーコマンドとの密接な連携にかんがみ、航空テロ対処、国賓等の空輸、弾道ミサイル等の警戒監視といった任務を遂行するに際し、的確な対応を行う上での基本姿勢として「掌握」を、また状況の急変に伴う十分な情報を入手できない中にあって全体最適の措置を講ずることの急務性から「即断」を選択したもの。
結びにあたり、総隊が一丸となって伊勢志摩サミットを安全保障の側面から成功に導くとともに、2020年開催の東京オリンピック等における支援活動の資を得ることを要望したい。
司令官メッセージのシリーズその4:「人をいとおしむ心の大切さ」平成28年8月29日
「司令官メッセージ」という伝達形式で、当時隷下部隊に気づきのあった事項を発信していた、第4弾です。毎年夏休みが終わるこの時期に、子弟をいとおしむ心の大切と部下隊員への気配りについて、メッセージを発したものです。
残暑から初秋へと向かう季節柄、夏季休暇により英気を養い、新たな意気込みを抱いて任務にj趨誉する隊員、一方で任務等との関係から、長期休暇を先延ばししなければならない隊員、それぞれにおいて職務に精励してくれていることに対して敬意を表します。
あなた達の子弟に思いを馳せる時、夏休みを終え学業再開へ向けた心の準備が十分ではない子弟も少なからずいらっしやるのではないでしようか。最近では、SNSに関連する悲しい人間関係のもつれ、ゲーム感覚の痛ましい事件を耳にする度に、あなた達の子弟が伸び伸びと育つ環境としては、何かと難しい時代になり、一層の気づき・目配りが必要なのかもしれないと心から思う次第です。
とかく繊細な思春期にある子弟におかれては、親として気持ちの上で寄り添うことが大切なのではないでしょうか。
また、隊務運営に目を向けると、成人したばかりの新隊員や課修者を迎え入れた部隊も多いことでしょう。当該隊員にとっては、自衛隊勤務における最初の長期休暇を終えた時期であり、共に学んだ同期や仲間達との別れの寂しさ、たった一人で配置された職場での不安、そして帰省による里心など、心の微妙な動揺が生じているかもしれません。特に、こうした若い隊員への意識的な気配りが極めて 重要なはずです。
今の時期にあって、あなた達にあらためて心に留めて欲しいことを敢えて付言させてもらいました。
繰り返しになりますが、常に「人をいとおしむ心」を持って、部隊勤務にあっては、あなた達が互いに粋を持ちつつ協力し合い、日々の勤務に遭進してもらいたいと思います。また、あなた達の子弟を、時間をかけて見守り寄り添い、しっかりと心のケアーを実践してもらうことを望みます。
人的戦カの確保にあっては、信頼につながる隊員間の相互交流、家族との団らんが原点だと私は確信しています。
これまで述べた心遣い等を、特にこの時期に実践してもらい、隊員諸官並びに、御家族に幸多かれと切に願います。
司令官メッセージのシリーズその3:「時代のすう勢に適った意識改革」平成28年7月吉日
「司令官メッセージ」という伝達形式で、当時隷下部隊に気づきのあった事項を発信していたものの、第3弾です。この時期はワークライフバランス推進強化月間であったことを受けて部隊・隊員に向けてメッセージを発しました。
ワークライフバランス推進強化月間 航空総隊司令官メッセージ
「時代のすう勢に適った意識改革」~全ては航空総隊から~
航空総隊勤務の隊員諸官においては、わが国を取り巻く環境の変化や幾多の事態対応の中にあっても、常に適切な措置を講じ、任務を完遂し、更に将来を見据えた総隊の隊務運営を追及し、就任の辞で示した「変化への対応」 「務持の保持」「改善と自律の追及」の統率方針の下精強かつ健全な部隊運営へ導き、個々の職務にも誠心誠意精励してくれていることに心より称賛するものである。そしてその隊員諸官を常日頃から日となり陰となり支えてくださっているご家族の皆様にも深く謝意をお伝えしたい。
このたびは、平素から航空総隊として推奨している人的戦力の質的向上としての施策のひとつである「意識改革」、その基盤ともなる、現在、省をあげて取り組んでいる「ワークライフバランス」、それを受けて航空自衛隊が平成27年に策定した「航空自衛隊における男女共同参画推進等に係る取組計画」などにより各種施策が示される中、28年7月から8月にかけては防衛省の「ワークライフバランス推進強化月間」とされており、この機会を活用して各部隊においては隊務運営の体制を確保しつつも、各級指揮官が率先垂範し、具体的な「働き方改革」の実践に大いに取り組んでもらいたい。
特に航空総隊司令部においては、現在、個人のリフレッシュや仕事と生活の調和を図り、個を充実させ、職場では業務の見直し、相互補完による隊員個々の多岐にわたる能力促進の機会の醸成を図ることを目的として「計画休暇」を推進中であるが、総隊全体としても浸透、定着が今後望まれる。ゆう活、超過勤務縮減、フレックス制度の活用、など自衛隊を取り巻く環境の変化、働き方の価値観の変化に防衛省としても柔軟に対応しつつあり、画期的な前進であることを歓迎するものである。
これらの画期的な取組みが、社会的な蓋然性に適い、航空自衛隊にとっての大きなメリットとなることは航空幕僚長のメッセージで誰われたとおりであり、航空総隊としても、繰り返しになるが、 「制度より風土、風土より上司」といわれるがとおり、上司自身の意識改革が重要であり、全隊一丸となって、各級指揮官の力強いリーダーシップの下、 「為せば成る」との強い意志を持ち、態勢を保持しつつも無駄の排除、隊務効率化の施策に創意工夫をもって遭進されたい。
隊員個々の心身のリフレッシュはもとより、ワークライフバランスの推進により介護・育児等と本来業務の両立に努め、何より男性職員が家庭を省みる機会を増やし、一方で各種制度を乱用することなく周囲への感謝と個々の努力を忘れることなく、隊員相互が助け合い、高い士気と生き甲斐を持ち得るよう人事・厚生面の施策に積極的に取り組むことを期すものである。
以上
司令官メッセージのシリーズその2:「総隊全隊員、一人一人に届けるつつじ便り」平成28年5月9日
「司令官メッセージ」という伝達形式で、当時隷下部隊に気づきのあった事項を発信していたものの、第2弾です。
隊員の自殺防止にかかる内容です。ちなみに、2021年における自衛隊の自殺者数は58名であったのに対して翌年2022年には、79名と前年度比で約1.4倍に増えたそうです。自殺防止は、いつの時代も部隊保全の重要な施策です。
航空総隊隷下隊員各位
あなたや私が所属している航空総隊では、昨年度における自殺者は、6名でした。詳細な内訳は控えますが、従前と同様に、年齢、階級、特技、補職先等に関する特定の傾向は見あたらないように思えます。新年度に入り1か月余りが経過したところですが、極めて残念なことに自殺事案が1件発生しています。
防衛省・自衛隊全体の自殺者数は、一般社会と同様、様々な施策等を講じていることあり減少傾向にあるようです。これ自体は、私達の任務遂行にとっても、また隊内の連帯感が図られていることを対外的に示すうえでも、良好な状況と評価することができるでしょう。
しかしながら、航空総隊全体としてみた場合、過去15年のデータの中で一度も、年度の記録「ゼロ」を達成したことはありません。
私の勤務方針が「全隊一丸 任務完遂」であることは承知のところだと思います。このうち、「全隊一丸」という言葉には、あなたや私が自らを強く律するとともに、他者の自殺防止に貢献する「気づき力」(あなた自身、家族、同僚に対する気働きとでも定義できるかもしれません)を常に働かせて、人が生命を絶つ行為を、何としても思い留まらせるという強い願いも込めています。
そこで今回は、関係部隊では、長期にわたり実任務を継続しているという耐久感、戦闘機部隊等の体制移行についての精神的ストレス等から、生じる可能性のある「気づき力」の低下を防止するとともに、黄金週間が終わり、いわゆる五月病に見舞われる不安を払拭し、心身共に健康を維持するために、別添の資料に目を通してもらうことを望みます。
なお、別添の資料1及び2(後日、掲載予定です)については、私がこれまでの部隊勤務の中で基地や特技が異なる、あなたの同僚達に話してきた自殺防止についての内容から抜粋したものです。
資料1は、私が西部航空方面隊司令官当時(平成25年4月5日)に配布した記事を再掲載したものです。
命の尊さ
警察庁の発表によれば、昨年の自殺者数は1997年以来15年ぶりに3万人を下回ったそうです。それでも2万7千名以上の方が自ら命を絶たれている。西空においても昨年度の自殺者はゼロではなく、どのような事情であれ、心からご冥福を祈るばかりです。
昨年度は通達類のみならず、「西部航空方面隊瓦版」と称する新規の部内通達の手法を整備した上で、自殺防止には十分に心がけていましたが痛限の極みです。新年度を迎え、あらためて「自殺者ゼロ」を念頭に、関連施策の推進にさらに積極的に取り組みます。
なお、私の娘(当時、中学3年生)が8年前に連合幹部会機関誌「翼」に投稿した記事の一部を以下に再記載します。隷下の隊員及びその家族の目にとまることを期待して。
『命の尊さについて』(一部抜粋)
今、私達が生きる時代は、自分から命を絶つ人、大人に限らず多くの中高生も人を傷つけたり、命を奪ったりと、命を粗末に取り扱う人が急増しています。私はせっかく戦争の無い平和な時代に生まれてきたのに、自分や人の命を傷つけては命が可哀想ですし、絶対にしてはいけない事だと思います。
私達は、生きたくても生きることもかなわずに、戦争で亡くなった人たち、日本の平和のために礎となって死んでいった人たちの命のことを深く考えて、自分を大切にして生きていかなければいけません。
今の平和な世の中で生きて、生活できる幸せを日頃から認識して感謝することと、一人ひとりの人間が自分の命と自分を取り巻くあらゆる命の存在と尊さを知り、向き合う事が現代には必要で大切なことであると思います。
資料2は、私が千歳基地司令当時(平成19年11月8日)に配布した記事を再掲載したものです。
隊員等の自殺について思うこと
去る11月2日、2空団所属隊員が自殺を図ったことは知ってのとおりです。当該隊員の心中に如何なる理由があったかは知る由もありませんが、告別式でお会いした御遺族や同僚隊員等の姿を見るにつけ、言葉に表すことができない無念さと深い悲しみがつのった次第です。
私自身、指揮官としての勤務歴の中で初めての隊員の死亡事故であったこともあり、大きな精神的衝撃と動揺を受けました。しかも、千歳基地に着任、ひと月もない9月26日の基地朝礼において自殺防止の観点から訓示(要旨については、下記の参考のとおり)をしていただけに、何とも言えず無力感で一杯でした。
今後は、関係隊員等のアフターケアを着実に行うとともに、連鎖を決して引き起こさないとの信念のもと、引き続き明るく楽しい隊務運営に精励することにします。
(参考:9月26日基地朝礼における訓辞の一部)
『私は笑いが大好きです。「笑う門には福来たる」「笑いは健康のもと」。・・・
(中略)・・・いまでも多くの自衛官が自殺しているのは知っての通りです。潜在的な自殺願望者は自殺者の何十倍と存在するようなデータもあります。しかし、私もあなた達も自ら死にたもうなかれ、自ら死の選択をしてはいけないのです。困難や苦難を乗り越えてこそ素晴らしい人生なのです。
自殺は自らの意志でやむをえずとして命を絶つケースが多いようです。しかし、残された親、兄弟、子供、友人、同僚にとっては大きな衝撃を受け、もどかしさと苛む気持ちをずっとその後の人生において持ち続けることになります。・・・(中略)・・・自殺でなくても、肉親の死は悲しみ以外のなにものでもありません。
だから、自ら死にたもうことなかれ。そのために自らの将来目標、人生設計をしっかり立て、少々無理してでも笑いながら仕事しようじゃないですか。また周りの同僚、知人にも心をくだいて、万一自殺するのではないかという兆候があれば救いの手をさしのべてやろうじゃないですか。その思いやりこそが千歳基地の団結を真に作り上げていくものだと信じています。以上』
司令官メッセージのシリーズその1:「総隊全隊員、一人一人に届ける桜便り」平成28年3月15日
航空総隊隷下隊員各位
「司令官メッセージ」という伝達形式は、総隊では初めての試みです。前職では昨年同時期にほぼ同様の内容を、支援集団隷下全ての部隊等に発信した経緯があり、今回はアーカイブ的に活用するものです。
平成27年度における総隊内の服務状況を総括してみると、規律違反件数は前年度とほぼ同数の〇〇〇件(3月1日現在)。また事故発生件数については、昨年度に比して半減(〇件)しており、まずまずの状態を維持していると言えるでじょう。
一方、総隊では、私的制裁を含む暴行、無断欠勤等の所在不明案件、私行上の非行等が増加傾向にあるのが気になるほか、世間ー般では、依然として、いじめ、危険ドラッグ等が大きな社会問題となっていることに鑑みれば、あなたや私、家族が健全な人生を歩む道程は、まだまだ危険が多いと言わざるを得ません。
こうした思いもあって、これまで総隊が取り組んできた「レジリエンス(精神的回復力)」(*現在は、他編合部隊等への浸透が図られているところと認識)をいっそう推進していくことが大切だと認識しています。
人生は順境と逆境の繰り返し。私自身はむしろ悪戦苦闘の連続との認識が強いためか、精神的な落ち込みが多々ありました。今後もあるでしょう。
しかし、その度に、同僚、家族、良質の本、過去の失敗に基づく反省等により、心身は回復、抵抗、復元、耐久し、今日に至っている次第です。
さて、今回は不安定な精神からの回復、不平・不満からの自発的治癒に少しでも役立ちはしないかと、私なりに考えた簡単な試みを提案します。
今は春欄漫。日本全国を「桜」前線が北上中。この桜を愛でながら、これまでの人生において桜にまつわる想いを追憶してみてはどうかというものです。人によっては、桜花とはいえ辛く憂うる想い出もあるかもしれませんが、一般的には、桜にかかわる回想では、喜び、楽しみ、懐かしさといった暖かい気持ちに包まれるのではないでしょうか。桜は、やはり日本人にとって特別な存在なのでしょう。
東日本大震災から丸5年が経ちました。当時、私は空幕装備部長の職にあり、桜花に関する思いを綴った「部長雑感」(平成23年4月13日付)を装備部員へのメッセージとして残していました。別添の資料(*「付録」として次の掲載)がそれです。
久しぶりに読み返してみると、精神的回復力を得るというよりは、自分自身が、心の癒しを桜に求めていたことや、同僚、家族に常に支えられていたことをあらためて実感できました。
心理学や医療の分野には疎い私ですが、本件を通じて健康、能力向上、リーダーシップを目的とする「レジリエンス」という概念のさらなる理解につながりを見いだした気がします。
以上
司令官メッセージのシリーズその1:「総隊全隊員、一人一人に届ける桜便り」平成28年3月15日の付録
以下の文章は、東日本大震災から丸5年が経過した時点で、私が空幕装備部長の職にあって、当時課班員に桜花に関する思いを綴った「部長雑感」(平成23年4月13日付)です。なお、市ヶ谷における「勤務の思い出」と重複しています。
東日本大震災の発災から1か月。この間、震災及び原発事故等のため昼夜分かたずの対応を余儀なくされ、気がつけば新年度となり早4月も中旬。
こうした国難たる事態お最中、昨夜来の風雨もあって東京の桜は散り始め、憂愁の想いがいっそう募るのは私だけではないだろう。
そこで今回の雑感は、これまでと趣を変え、季節柄の「桜」にまつわる個人的想いを記述してみたい。コーヒーブレイクにでも一読されたい。
桜。人に多き思い出を残す花のひとつ。未曾有の大規模震災と断続的余震に国全体がまさに揺れ動く今年の桜の開花は、私にとっても極めて印象深いものとなった。
F2戦闘機の会合参加を主たる目的とした米国出張のため成田を発つ日(3月28ョ)の早朝、いつものように自宅付近をスロージョギング。この時、桜の蓄はようやく先端が色づき始めた状態だった。その20時間経過後から帰国間際までワシントンDCの各所で、見事に咲き誇る桜花を観ることができた。
同地滞在中、天候不順だった最終日の早朝を除き同行していた部下二人と共に、気温数度という寒気の中、桜を時折愛でながらのランニングは実に爽快だった。無理やり伴走を頼んだ二人には感謝している。
米国到着した当日のタ刻、空軍参謀本部A4部長から自宅でのタ食会に招待された。ここでも桜が話題となる。部長自身から、ワシントンDCの桜(ウェブ資料には苗木3, 020本とある。)は、1912年に当時の市長・、尾崎氏が米国に贈ったもので、今年99年目となる旨の説明を受けたのに加え、市販の関連本をプレゼントされた。
米防衛駐在官から「ワシントン桜物語」の概要について事前に話を聞いていたのでなんとか救われたが、そうでなければ少々恥ずかしい思いをするところだった。次回の海外出張時には訪問先の地誌等も学習すべきと反省。(中略)
今次の震災において、「トモダチ作戦」等による米国支援が功を奏して事態の改善が図られた暁には、来年の「ワシントンDC桜祭り」に100周年と震災復興の記念としてあらためて桜木を贈ってはどうだろうか。もちろん日本国としてである、
先週末(4月9日・土曜日)、同期生の法事があって供養のため目黒の菩提寺を他の同期生と共に訪間。4年前に病気のため急逝した同期生である。祥月命日は4月13日。桜の開花が遅れる年は目黒駅から先の寺に行く途中には、目黒川沿いの有名な桜並木がある。
奥様にしてみると、桜を観るのはただただ悲しいという話を同期生伝えに聞いた。領くしかない。彼は、松島基地・基地業務群司令が事実上、最後の補職先であったことから、奥様にとっても松島基地は忘れられない存在。今次の震災でも慰問品を送られたとのこと。
今週日曜日(d月10日)、今年の桜も見納めとなるやもしれぬとの思いから、都知事選の投票後、妻と二人で自宅近辺の桜花の観賞に自転車で出かけてみた。この日は、例年だと「桜まつり」が催され在住の芸能人が出演するのだが、今年は震災のため自粛ではなく「震災復興支援イベント」として開催された。
「馬事公苑」及び付帯施設であるJRA敷地内、東京農業大学前の数百メートルに及ぶ桜木のアーチを満喫。今の場所に住み着いてちょうど10年。これほど桜を観て回った年は初めてだった。(中略)
想い出を語れば切りがないが、桜が葉桜になる前に、各人も桜を観ながら桜にまつわる出来事を回想してみてはどうだろうか。
*当時(平成23年4月)作成した原文からは、個人名を伏せるとともに、文章の一部を省略。
横田基地勤務時代(平成27年12月~平成28年12月)の思い出
横田基地が最後の勤務地となりました。当時は、北朝鮮の弾道ミサイル対処のために基地外に出ることがままならない時期で、家族に時々慰問してもらっていました。
毎朝のように官舎に隣接する米軍フィットネスクラブで汗を流し、航空自衛隊の食堂で朝食をとっていたことが懐かしい限りです。
ただし、当時添付していた記事説明用の写真が検索できないのが悔やまれます。→*印刷物で当時の写真を見つけましたので、フォトスキャンして関連記事ごとに添付します。電子版の画像に比較するとかなり不鮮明ですので、拡大機能は付けておりません。(令和6年2月)
日米共同の実効性を高めるため:平成28年2月2日
先月中旬から今月初めにかけて日米共同統合演習(指揮所演習)が実施されたことは、先に統合幕僚監部より報道発表があったとおりです。航空総隊にあっても、私はもとより総隊司令部等から幕僚が参加し、本年度における練成訓練の集大成を図りました。
指揮所演習とは、実地に部隊等の全部又は一部を活動させる「実動演習」とは異なり、関係部隊司令部間の指揮幕僚活動を演練することを目的として行うものです。
今回21回目を迎えた当該演習においては、新ガイドラインで規定された日米同盟調整メカニズムについても演練・検証して、共同統合運用能力の向上を図ることを主な目的としていました。
統合幕僚長の指揮の下、先見性及び計画性をもって刻々と変化する情勢・状況に適応するための指揮所活動を行い、それと同時に日米関係部署による各種調整を行いました。共同統合運用能力の向上という目的の達成にふさわしい鍛錬と検証の場となった次第です。
こうした演習・訓練を通して、「頭の体操」「知恵出し」をすることにより、実践の場で臆せず気負うことなく、そして柔軟に最適対処策を案出することが可能となるわけです。特に、日米空軍種間において、概念、計画、考え方等について、一つ一つ合意形成を図っていくプロセスを演練でき、貴重な経験を得ることができたと考えます。
各種演習では、指揮官及び幕僚の個々の能力向上もさることながら、やはり司令部内、関係部隊間といった組織力(チームワーク)を高めていくことこそが最も肝要です。
本演習においては、総隊司令部と各種調整を実施した米空軍の関係部署との間で、相互の理解と信頼がさらに深まり、運用・後方等分野ごとの共同要領の整合や検討の資を得られ、大いに成果があがったと実感しています。
敬礼は国籍を問わず:平成28年2月16日
空自にあって、基地とは、部隊又は機関が所在する施設であり、隊務運営及び任務遂行にあたって重要な役割を果たす単位のひとつです。その基地ごとに基地司令が置かれており、当該司令は、自ら指揮する部隊のほか指揮系統以外の部隊を統制しながら、基地の警備・管理、規律の統一、災害派遣等を行わなければならない重要かつ遣り甲斐のある職務です。私自身、10年前に千歳基地司令を拝命し、同職務を遂行するとともに、基地の発展と地域の安定に関わった経験があります。
現在、空自の基地等(基地及び分屯基地)は73箇所。横田基地は総隊司令部等が平成24年3月に府中基地から移転した際に設立された最も新しい基地となります。今春で4年が経過しますが、この間、基地司令を兼ねた作戦システム運用隊司令が、米軍との密接な諸調整を行いながら、基地内外における勤務及び生活の改善に努めてきています。
日米が同居する横田基地において、感心させられる事のひとつに、日米隊員間の敬礼の励行があります。横田基地内における日米間の敬礼要領は制定されているわけではありません。空自側は基地司令が率先して、自衛隊の礼式に関する訓令に基づき米軍人にも敬礼をするよう教育しています。米軍側でも同様の教育指導がなされていると聞き及んでいます。両国隊員が相互に敬礼する姿は、日米共同が実効性を伴っている証左と言えるのではないでしょうか。
敬礼の励行は信頼醸成の第一歩。先の礼式には、「敬礼を受けたものは、答礼を行うものとする」とも定められています。私も立場上、頻繁に日米両国隊員から敬礼を受けます。国のいずれを問わず、欠礼(答礼を怠ること)のなきよう、基地内の移動中には特に留意する日々です。
東日本大震災から5年を迎え:平成28年3月11日
我が国にとって、未曽有の震災であった東日本大震災から5年が経過。当時、自衛隊は全力を持って、原発事故対応から被災者への救難物資の輸送まで幅広く、陸海空の多くの部隊が昼夜を分かたず活動していことが思い出されます。
そのような当時の自衛隊の活動に対して、世界各国・地域・国際機関等から様々な協力支援をいただき、航空総隊を代表して心から御礼を申し上げます。特に米軍からは、「トモダチ作戦」に基づき捜索救助活動、被災者の生活支援、空港、港湾、道路等の機能回復等に多大な貢献をいただいたことに、あらためて感謝する次第です。
米国および関係国との防衛協力は、各種事態の抑止及び対処の実効性を確保する上で、重要な要素です。このことを踏まえ、航空総隊としては、これらの国々との相互運用性の向上のため、今後とも共同訓練等の場を大いに活用するとともに、信頼・友好関係の向上に寄与していく所存です。
退官する親を敬する子の姿:平成28年3月22日
3月上旬、米空軍横田基地において、在日米軍及び第5空軍再先任上級曹長(主な職務は司令官の補佐)の交代式、引き続きこれまで同職にあった上級曹長の退官式が挙行されました。退官した彼は前職の三沢基地第35戦闘航空団でも最先任上級曹長の職を務め、通算6年の在日勤務であったとの紹介がありました。
自衛隊からも職務上関係のあった陸海空自衛隊関係者が出席。私も招待を受け参列。式典の中で特に印象に残ったのは、退官上級曹長の子息である上等空兵(空自の空士長に相当する階級)が勤務先のアラスカから来基し、式典の檀上にて退官する父への想いを語る姿でした。
この時、私は式典の席上にあって、下記(*)のことを思い出していました。日米間で、国・民族としての文化や組織の式典要領は異なるものの、子が親を慕う姿、こうした親子の絆を目の当たりにする周囲の者の感激は、変わらないものなのだと実感した次第です。
*平成19年10月20日(土)付の千歳基地ホームページに掲載した団司令の雑感「定年退職自衛官の背中を見つめて」より
『先月ある定年退職自衛官(最後の勤務地が千歳基地)の息子(やはり千歳基地の勤務)が流した涙を思い出しました。
他の多くの部隊でも行われているように、第2航空団においても、退官者は階級にかかわらず庁舎前において当該者の所属する部署のみならず、当日勤務する者が大勢で見送りをすることが以前から慣わしとなっています。
その日も退官式の最後に現役隊員が列を作って見送りしました。この際、その列の中に退職隊員の息子がいることを知り、すでに涙している彼を私の傍らに呼び、父親を見送らせたことがありました。
息子が流す涙から、この子が父親に対する尊敬の念、家庭での父の子に対する躾や愛情の深さ、そして彼の自衛官としての意気込みなどをうかがい知ることができて、爽やかな気持ちになったことを思い出します。』
日米親善のための桜プロジェクト:平成28年4月6日
今は春爛漫。日本全国を「桜」前線が北上中。各地で様々な桜を愛でながら、これまでの人生において桜にまつわる想いを追憶されているはずです。人によっては桜花に辛く憂うる想い出もあるかもしれません。しかし、一般的には、喜び、楽しみ、懐かしさといった温かい気持ちに包まれるのではないでしょうか。桜はやはり日本人にとって特別な存在なのでしょう。
先週末、横田基においても日米友好観桜会が開催。総隊司令部等が所在する庁舎に最も近い満開の桜木のもとで、互いにパートナーシップ、フレンドシップを深め合うことができました。
米国本土においては、ワシントンDC・ポトマック河畔の桜並木及び関連のフェスティバルが有名ですが、横田基地内の桜も大振りの古木で見応えがあります。参加した日米の隊員同志は、春の風情を満喫しつつ、肩組み大いに語り合っていました。
そもそも空自と米空軍による花見の始まりは、府中基地にようです。昭和50年、米軍が同基地から現地駐留している横田基地に移転したのに伴い、府中基地が空自に全面返還されたことを機に、翌年春に第1回となる「府中基地観桜会」が実施されたとのこと。
その後、開催要領等の変更や開催中断の時代もあったようですが、府中基地では現在でも横田基地から米空軍関係者を数十名招待して観桜会が行われています。今年は第1回を起点とすると40年目の記念の年に当たります。
また、空自・横田基地に焦点を当ててみると、今年度は移転から5周年の節目の年。これをきっかけに、府中基地のみならず多くの空自基地等と同様に、横田基地においても総隊司令部等庁舎付近、基地内に設置されている将官宿舎及び隊舎周辺に桜木を植樹するプロジェクトを発動するよう基地司令と共に企画。総隊司令部等の移転10周年、あるいは空自創設100周年を目標に日米親善に貢献する遠大なプロジェクトになればと夢を膨らませています。
転入者の即戦力:平成28年4月18日
年度の変わり目は、人事異動の時期でもあります。この春の総隊司令部からの転出者は、27年度防衛諸計画に基づき円滑に業務を実施したのはもちろんのこと、関係部署と入念な調整の上、28年度防衛諸計画の策定等に尽力してくれました。昨今の我が国を取り巻く情勢等から、任務の遂行と業務の処理には相当の時間と労力を費やしたはずです。彼ら/彼女らが職責を全うしてくれことに対して心から敬意を表します。入れ替わりに気鋭の幕僚が転入。それぞれに与えられた職に邁進し、28年度に総隊が掲げる航空防衛力の造成にも努めてもらうことを期待します。
総隊隷下部隊等における全ての異動者にあっては、まずは新しい生活基盤を確立した上で、速やかに職場環境に順応してもらいたいものです。来月には伊勢志摩サミットの支援、その後には戦闘機部隊等の体制移行と、これまで周到に準備してきた部隊活動や事業計画が控えています。新職務に対する不慣れから生じる不安があるかもしれませんが、気概をもって任務に臨みましょう。
私個人は、入隊以来20回の異動を経験。その都度、「とにかく最初の一週間を懸命に、次に一か月を全力で…」と一日も早く所属部署の戦力となりうるよう、自らに言い聞かせていました。
その際、必ず唱えていたのが「Well begun is half done(初め良ければ、半ば成し遂げたのも同然)」。この精神をもって着任当初から所属部署等における重責を担う指揮官又は幕僚として、積極的に行動することを要望します。
もう20年以上前になりますが、その時仕えた上司から着任直後にいただいた訓示が思い出さます。
「健康管理はとても大切。体調の良し悪しは自らだけが知りうる。自己管理の不適正が、組織における人的戦力の低下を招くのだから。」
命の尊さ:平成28年5月10日
警察庁等の発表によれば、昨年の自殺者数は前年に比して5.5%減少したとのことです。それでも2万4千名以上の方が自らの命を絶たれています。性別では約7割が男性、また年齢別では40及び50歳代が3割以上を占めています。
航空総隊においては昨年度の自殺者数6名、今年度も1名を亡くし、心からご冥福を祈るばかりです。
私は、総隊における勤務方針に「全隊一丸 任務完遂」をかかげています。このうち、「全隊一丸」という言葉には、所属する隊員が自らを強く律するとともに、同僚等の自殺を未然に防止する「気づき力」を常に働かせて、人が生命を絶つ行為を、何としても思い止まらせるという強い願いも込めているつもりです。
大型連休であったゴールデンウイークが終わりました。この時期、いわゆる五月病に見舞われる不安を払拭し、心身共に健康を維持してそれぞれに与えられた職務に精励していきましょう。
なお、総隊隷下の隊員及びそのご家族の目にとまることを期待して、もう10年以上も前になりますが、私の娘(当時中学3年生)が空自連合幹部会機関誌「翼」に投稿した記事の一部を、以下に再記載します。
『命の尊さについて』(一部抜粋)
「…。今、私達が生きる時代は、自分から命を絶つ人、大人に限らず多くの中高生も人を傷つけたり、命を奪ったりと、命を粗末に扱う人が急増しています。私はせっかく戦争の無い平和な時代に生まれてきたのに、自分や人の命を傷つけては命が可哀想ですし、絶対にしてはいけないことだと思います。私達は、生きたくても生きることもかなわず、戦争で亡くなった人たち、日本の平和の礎となって死んでいった人たちの命のことを深く考えて、自分を大切にして生きていかなければいけません。今の平和な世の中で生きて、生活できる幸せを日頃から認識して感謝することと、一人ひとりの人間が自分の命と自分を取り巻くあらゆる命の存在と尊さを知り、向き合う事が現代には必要で大切なことであると思います。」
伊勢志摩サミット支援活動の先に:平成28年5月31日
北海道洞爺湖サミット以来、8年ぶりに日本において開催され、世界経済の政策協調を焦点とした伊勢志摩サミットは、不測の事態に見舞われることなく、予定どおりの日程を終え閉幕。各国首脳による宣言採択からは、安全保障問題も含め、我が国政府としても多大な成果が得られたのではないでしょうか。
期間中、航空総隊は支援活動を整斉と実施することができました。今次のサミットでは、過去最大となる警察官の動員数と報道されていたことから、様々な事案・事態が発生する可能性は決して低くはなかったようです。総隊としては、こうした予断を許さない状況の中で、組織が有する本領の発揮に努めたところです。
世界の主要国等が注目した国家イベントに関われたことは、まさに誇りです。また期間中、微事故も発生させず、人的・物的戦力の低下を生じさせなかったことは、関係隊員各人が自らを強く律した結果だと確信しています。
今回の伊勢志摩サミットの支援活動を通じて得られた成果等については、速やかに整理、保管し、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックをはじめとする将来の国家的行事における「国家主催の保持 国民の安全確保」の資として後進に伝承していくこととします。
「航空自衛隊安全の日」にあたり:平成28年7月6日
「航空自衛隊安全の日」(毎年7月1日)は、全ての航空自衛隊員が安全確保の重要性を再認識し、事故防止を図るために設定されたもの。その設定の契機となったのは、平成11年から12年にわたり連続して発生した航空大事故でした。
航空自衛隊は、その創設から今年で62年目。航空総隊は、航空集団司令部等が廃止され名称変更してから58年の時が経過。あまたの先人が、そして私達現役も、「安全」について、その意義を噛みしめ、各種施策を繰り出し、後進を教え育むなど、積極的に「取り組んできました。これからも、その姿勢は変わるものではありません。
人は、いかなる時も「安全」を怠ってはなりません。このためには、「生命は尊くも儚きもの」という強い念が意識の根底に定着していなければなりません。常に、生存とそのために死傷する可能性があるというリスクに対する関心を持ち続けなければならないのです。
自らが安全に対する意識を疎かにすれば、他人や組織自体をも危機にさらす羽目にきっと陥るでしょう。命あるところ常に危険がつきまとうのです。したがって、安全の飽くなき追求は、人にとって使命であるはずです。
結びにあたり、志半ばにして、その職に殉じられた航空自衛隊409柱の御霊に対し、航空総隊を代表して、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
基地祭の思い出:平成28年8月26日
横田基地では、「Japanese-American Friendship Festival」と銘打って米空軍が毎年9月に友好祭を開催しており、一昨年からは、空自横田基地も横田祭を共催しています。ちなみに、今年の横田基地日米友好祭は、9月17日(土)・18日(日)の2日間、このうち空自は18日のみに独自のイベントを催します。詳細は空自横田基地ホームページをご覧いただければ幸いです。
空自の各基地及び分屯基地では、航空祭、基地開庁祭と称する基地等をあげての行事が毎年開催されます。基地航空祭等は、地域住民等との交流を目的とした重要なイベント。したがって、主催する基地司令及び分屯基地司令にとっては、重要な年中行事のひとつでもあります。しかも、各種航空機による展示飛行を伴う場合が多く、当日の天候次第では実施演目や入場者数に大きく影響します。また、過去においては、不測の事態対応等を考慮して、やむを得ず中止又は規模縮小するケースもありました。
私自身は、これまで八雲分屯基地司令と千歳基地司令の職にあった時、基地航空祭を主催した経験があります。当時の心境については、以下(それぞれの補職時に作成した「雑感」を再掲載)のとおりです。基地司令等の立場にある者の達成感や落胆ぶりが少しでも伝わればと思います。現在、基地司令等の職にある後輩指揮官も一喜一憂しているのではないでしょうか。大切なのは、来訪者をもてなす心と各種事故の防止です。基地司令等がこれらを常に念頭に置き航空祭等の運営にも尽力するとともに、天運に恵まれますよう祈念しています。
*八雲分屯基地司令時代の雑感:タイトル「基地開庁祭、感激と感動のうちに成功裡に終了」(平成10年9月1日付)
『平成10年8月8日(土)、この日、八雲分屯基地で目にした事は生涯忘れられない。昨年、基地開庁20周年という節目の年に、例年にない規模での各種行事を計画していたにもかかわらず、野田生川に架かる国道5号線の架橋が損壊するほどの豪雨により、全ての飛行展示を中止した経緯があればこそである。第11飛行隊(ブルーインパルス)及びロック岩崎エアロバティック・チームの招請について、紆余曲折を経て実現させ、開庁祭当日、RF-4、F-15、U-125、UH-60と共に八雲基地上空で、これら華麗な演技に魅了された時はまさに感無量であった。(後略)』
*千歳基地司令時代の雑感:タイトル「快晴下での基地航空祭は大盛況、天運に感謝!」(平成20年8月11日付)
『航空祭(基地開庁50周年記念)が終了した昨夜は、ひとり官舎で祝杯を挙げました。缶ビールがこれほど美味しいものとは。昨年9月の着任以来、1年間にわたる基地の主要行事を、すばらしい天候に恵まれた航空祭をもって、基地所属隊員と共に、締めくくれたことにただただ感謝です。(中略)今夜もまだ航空祭の余韻と共に、1年間の数々の行事を振り返るつもりです。いつもよりアルコールがすすみ、久しぶりに熟睡できそうです。』
平成28年5月28日
「伊勢志摩サミット支援任務を完遂した全部隊等を称賛!」
北海道洞爺湖サミット以来、8年ぶりに日本において開催された伊勢
志摩サミットは、不測の事態に見舞われることなく、予定どおりの日程
を終え閉幕。参加国の要人等は、すでに帰国の途につかれている。
当該サミットにおいては、世界経済の堅調化のための政策協調が主体
であったものの、我々の基本任務にかかわる北朝鮮の非核化、海上安全
保障、テロ対策等、安全保障上の議題についても、各々に合意形成が図
られ、我が国政府として一定の成果が得られたものと思料する。
、j 航空総隊によるサミット期間中の諸支援活動を総括してみると、一部
装備品等の不具合が生じたが、代替手段を講じ任務遂行に影響を及ぼす
ことなく、整斉と実施することができた。
今次のサミットでは、過去最大となる警察官の動員数と報道されてい
たことから、様々な事案・事態が発生する可能性は決して低くはなかっ
た。総隊としても、こうした予断を許さない状況、並びに変化する航空
気象に適応し、空自組織が有する本領の発揮に努めたところである。
�
世界の主要国等が注目した国家イベントに関われたことは、まさに誇
りである。また期間中、些細な事故も発生させず、人的・物的戦力の低
下を生じさせなかったことは、各人が自らを強く律した結果だと確信し
ている。
かかるように、総隊が今次のサミット支援活動をほぼ計画どおり実施
し得たのは、航空支援集団、航空教育集団、補給本部等、空自の関係部
、.ン 隊はもとより、他省庁、関係自治体、陸海関係部隊等との密接な連携による賜物と関係各位に深く感謝する次第である。
結びにあたり、伊勢志摩サミットの支援活動を通じて得られた教訓等
を決して散逸させることなく、2020年開催の東京オリンピック等を
はじめとする将来の国家的行事における安全確保の資として、後進に継
承されんことを切に要望したい。
航空総隊司令官 空将 福江広明