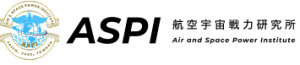「強靭性・持続性のあり方」
Ⅰ 参考資料等(各資料の「概要」と「着目すべきポイント」は、付紙を参照)
・ Air Force Doctrine Note 1-21“Agile Combat Employment”Dec.1, 2021
・荒木淳一、第6回現代戦研究会資料「米空軍のACE構想について」令和4年10月
・JFSS第3回政策シミュレーション成果報告書「徹底検証:新戦略3文書と台湾海峡危機―2027年に向けた課題―」2023年7月18日
・「国家防衛戦略について」(令和4年12月16日)
https://www.cas.go.jp/jp/siryou/221216anzenhoshou/boueisenryaki.pdf
・「防衛力整備計画について(令和4年12月16日)
https://www.cas.go.jp/jp/siryou/221216anzenhoshou/boueiryokuseibi.pdf
Ⅱ 発表の要約(発表者作成資料の全文は、PDFファイルを表示)
1 ポイント1:防衛3文書「持続性・強靭性」における特徴
○整備の達成時期の明示…これまでの諸計画と一線を画す具体性
・2027年度までの5年間(予算措置あり):
1)「弾薬・誘導弾の数量を増加」
2)「整備中以外の装備品が最大限可動する体制を確保」
3)「有事に備え、主要な防衛施設を強靭化」
4)「保管に必要な火薬庫等を確保」
・おおむね10年後まで(予算措置未定):
1)「弾薬・誘導弾の適正在庫を維持・確保」
2)「可動率を維持」
3)「防衛施設をさらに強靭化」
4)「弾薬所要に見合った火薬庫等をさらに確保」
○7つの柱のうち最も手厚い予算配分
・今後5年間での「最優先課題」として、総予算43.5兆円のうち、15兆円(約34%)を占める。
・弾薬・誘導弾へ2兆円、装備品の修理へ9兆円、施設の強靭化へ4兆円。
・一方で、5年後以降10年後までの予算見通しは示されず。
○今ない装備品(これから開発するもの)も含めて明示
・「SM-3ブロックⅡA」「PAC-3MSE」など今ある弾種に加え、「12式地対艦誘導弾能力向上型」「03式中距離地対空誘導弾(改善型)」など、新たに開発するものも含めて個別の弾薬名を列挙して必要量を整備する方針を明示。
2 ポイント2:防衛3文書「持続性・強靭性」の評価
○定性的な目標ではなく、予算裏付けを伴う具体性ある計画へと変貌
⇒2027年を基準としたタイムライン
○基盤的防衛力構想からの脱却の試み、足りないものへの率直なアプローチ
⇒具体的な脅威を想定した態勢整備に着手
⇒「タマに撃つタマが無いのがタマに傷」の解消
⇒不足している状況を提示
⇒「手の内を明かさない」でごまかさない透明性
○計画執行の困難さ、タイムラインの妥当性の問題
⇒現行ルールでの膨大な事務所要
⇒民間生産能力の大幅拡大が前提
⇒新たな技術の開発から装備化、量産までのタイムスパンの短さ
⇒防衛省外(市民・自治体・他政府機関等)の理解と協力が不可欠
3 ポイント3:防衛3文書にみる「持続性・強靭性」の論点(課題)」
○想定する我が国防衛作戦の姿は?
⇒どのような作戦を展開しようとしているのか(特に新たな領域の活用)
⇒「やりたいこと」は示せたが、「どのように」はこれから
1)統合運用の行方は(指揮・通信、装備の共通化など)
2)同盟国との連携は(共同開発、共同生産、共同備蓄、戦時融通など)
○米中確執で切迫する、より高いレベルの日米連携の必要性から見て
⇒単なる備蓄増だけではない、「運用する体制」こそ強靭化すべき
1)ますますネットワーク化が進む米国・同盟国との連携
・日米によるキルチェーン構築
・グローバル化したF35の部品供給の円滑化
2)高度な情報共有に求められる情報セキュリティとコミュニケーション力の向上
⇒防衛装備品が国産主体の国は、実は少ない−−課題は最先端技術と実用性
・国内産業保護と国外連携強化とのバランス
付紙
「強靭性・持続性のあり方」の参考資料
- Air Force Doctrine Note 1-21“Agile Combat Employment”1, 2021
② 第6回現代戦研究会資料「米空軍のACE構想について」令和4年10月
③ JFSS第3回政策シミュレーション成果報告書「徹底検証:新戦略3文書と台湾海峡危機―2027年に向けた課題―」2023年7月18日、https://www.jfss.gr.jp/taiwan_study_group
上記資料の概要及びポイントについては、別紙第6「機動展開能力・国民保護」の各項目を参照するほか、ここでは米空軍のACE構想について説明文を掲載する。
1 ACE(Agile Combat Employment)構想とは
〇定義:統合的抑止の下で戦闘力を作り出すと同時に生存性を増加させるため、脅威の時間軸の中で実行される能動的、受動的な機動の運用枠組み(AFDN-1-21(1 Dec.2021))
・中国のA2ADの脅威:弾道ミサイル、巡航ミサイル等+サイバー・宇宙
・地理的特性:広大な海洋域、圧倒的な距離的優位性は中国
・航空戦力の本質的弱点:地上において脆弱であること、戦力発揮を基地等の作戦基盤に依存すること、空間を占有し続けられないこと等)
⇒上記を克服し、戦力発揮を担保する為に航空戦力を機動、展開、分散・離合させる運用構想
〇ACEの運用枠組み(AFDN-1-21(1 Dec.2021))
・5つの核心的要素と3つの統合機能;①態勢(Posture)、②指揮・統制(Command &Control)、③展開と機動(Movement & Maneuver)、④防護(Protection)、⑤維持(Sustainment)+❶情報戦(Information)、❷情報(Intelligence)、➌火力(Fires)
・ACEを実現する鍵;1)展開先で多機能発揮できるエアマン、2)任務に応じた戦力パッケージ化(敏捷性と任務リスクとのバランス)
2 背景と経緯等
〇オバマ政権下における対中軍事戦略を巡る議論の迷走(ASB、OSC、JAM-GC等)
〇トランプ政権下における対中戦略の大転換(戦略的競争相手:NSS2017/NDS2018)
〇米空軍の葛藤;三重苦(規模の縮小、レディネスの低下、近代化の停滞)の克服+非対称の脅威への対応(中国のA2AD、サイバー・宇宙)+「マッスル・メモリー」の回復
⇒CQ.ブラウン大将「変化を加速させるか負けるか:ACOL」、統合全領域作戦(JADO)/
JADOの指揮・統制(JADC2)等の追求、宇宙軍の創設(宇宙領域の作戦領域化)、ドクトリン等の見直し(Mission Command、ACE、JADO/JADC2)、ABMSの追求
〇ACE構想の芽生えと急速な発展
・2018年、当時のPACAF司令官 CQ.ブラウン大将の下、ACE概念の明確化(PACAF司令部における意見交換において1枚のコンセプト・ペーパー(ハブ&スポークのクラスター運用構想)として提示)
・各種訓練、演習等における実証を通じて構想を洗練、2021年AFDN1-21ドクトリン・ノートを発出(ドクトリン化の途上⇔変化し続ける概念との認識も)
・2022年、PACAFでIOCを確認、実戦環境下でのFOCに向けて準備中
3 PACAF提示のACEの運用構想(案);
〇何故ACEが必要か;ハワイ、豪州、米本土からの距離の問題と中国のA2AD脅威に対する地上の航空戦力の脆弱性の問題への対応
〇中国の長距離精密打撃力(DF-26,H-6K,DF-21)の射程内で、空母打撃群や第5世代機(F-22/F-35)を失いたくない。
〇長距離打撃力の攻撃から生き延びつつ戦力発揮する為に、分散し、敵艦艇を攻撃・阻止する為に再集合するのがACEの考え方。戦域を適切に整え、戦力を展開し、機動させ、C2を確保し、戦力を維持・発揮する為の構想。
〇精密誘導攻撃をかわすためには、航空機の分散、デコイの活用が必要。また、被害局限・衛星からの被探知回避の為、簡易掩体等を活用。
〇戦闘機等は基本的にインサイド・フォースとして活用する考え。グアムはDF-21Dの射程外であるものの、DF-26の射程内のため防御が圧倒される可能性あり。しかし、在地の戦闘機に対してC2を維持し、ミサイル攻撃の警報が15分前までに出せれば、空中退避する等してインサイド・フォースとして活用は可能。
〇第5世代機(F-22/F-35)の配備は、グアムを中心にした周辺の島々に概ね4個SQ(F-22×1個SQ、F-35×3個SQ)程度の分散配備を考えている。日本に所在するF-35やその他の戦闘機は、日本国内で分散させる考え。
〇B-52/B-2、空中給油機、AWACSといったハイバリュー・アセットは、アウトサイドに配置して安全を確保しつつ、インサイドで柔軟に運用するアウトサイド・フォースとして活用。運用上の工夫(ダブルクルーでの連続運用、ホット・リフューエルによる在地時間の局限等)で70%以上、空中での運用が可能。
〇分散運用先での後方支援(燃料、弾薬、スペアパーツ等)が受けられることがACEの大前提。第一列島線上に事前集積しておくことが必要であり、それによって作戦準備期間を短くし、事態に即応することが可能となる。平時の費用対効果という考え方と有事のレジリエンスという考え方のバランスをとって燃料タンク等の整備を行う必要あり。
〇ACEの作戦構想(CONOPS)を航空自衛隊と共有し、共同することで、日米の航空戦力運用の柔軟性を向上させ、強靭性を高めることが可能。F-35の日米共同での整備補給等が可能。ACEには日本の民間飛行場等の使用が不可欠。
4 ACEの課題
〇「アクセス」の不確実性+受動的防御策の強化予算の不足
・分散運用する飛行場等の確保(民間飛行場等の使用、平時からの継続的訓練)
・消極防衛(分散、掩蔽、被害復旧等)の優先順位
〇機動分散先での後方補給支援の担保(事前集積、移動・展開、多機能発揮可能なエアマンの養成と維持)、C2系統の確保
〇統合運用の一環としてのACE(被害復旧、基地防護、基地防空、脅威下でのLogisticに関する他軍種との役割分担)
5 日米共同におけるACEの意義
〇戦略的な意義;
①米中間の戦略核戦力が均衡化する傾向(相互抑止関係の成立)の下で「安定・不安定の逆説」の先鋭化を回避するための通常戦力バランスの均衡化を図る重要な手段
②米軍の航空戦力を戦域内に繋ぎ止める手立て(コミットメントの担保)
〇作戦・戦術的な意義;
①日米の航空戦力の脆弱性の克服、生存性確保、継続的な戦力発揮を担保する手段
②日米共同による航空戦力の相互補完
③台湾に対する着上陸戦力を撃破・阻止し得る航空戦力態勢の維持(拒否的抑止)
☆懲罰的抑止と拒否的抑止のバランス、核戦力と通常戦力によるシームレスな抑止
6 わが国として取り組むべき事項
〇特定公共施設利用の柔軟性、適宜性を担保する為の法改正(武力攻撃事態法等)
〇日本版ACE(≒飛行場群運用構想)を実現するための体制・態勢整備
・分散、機動先での後方補給支援体制の確立(事前集積のために地積確保・事前集積用資器材の整備、弾薬等の機動配分・保管を可能とするコンテナ等の整備、戦術輸送・端末輸送能力の強化(C-130、CH-47等の増勢)、移動式燃料タンクの整備、KC-130等によるホット・リフューエル機能の整備)
・機動分散先でのC2系統確立(モバイルC2機能の整備)
・統合・共同による被害復旧能力の強化(陸空の滑走路被害復旧能力の強化、所要の器材・資材の整備、日米共同による滑走路被害復旧能力の向上)
・脅威下、被害状況下での簡易整備・補給に関わる基準の策定、訓練等の実施
・操縦者による燃料補給、簡易点検等の自己完結的再発進能力の向上、訓練
・機動・分散運用を支援できる多機能な能力を持つ整備員の養成、管理
〇日米共同作戦の実効性向上のための取組み
・対中軍事作戦構想の擦り合わせ(エンドステート、エスカレーション・コントロール要領、平時からグレーゾーン、有事に至る各種作戦(邦人輸送、NEO支援、先島諸島住民避難、難民等対処、尖閣対応、南西諸島防衛等)の擦り合わせ
・日米共同のC2系統の確立、日米共同でのACE運用要領の確立