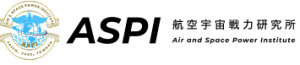1 勉強会の焦点
上半期の研究テーマである「『包括的抑止戦略』構築の為の課題と取り組みについて」を考えるにあたっては、今回は米国において活用されているネットアセスメント手法について関連資料を基に理解を深めた上で、我が国のネットアセスメント動向等を議論する。
2 意見交換に先立つ参考資料の要点説明
以下の資料のポイントを約45分で説明。なお、それぞれの特徴は次の通り。
(1)「ネットアセスメント関連記事等」
ア 電磁波領域における戦い – 米国ネットアセスメントによる評価・分析」海自幹部学校(コラム155 2020/03/16)
→ CSBAレポートに関する記事で、ネットアセスメントの目的、競争相手依の強みと弱みを評価して戦略計画を立てる手法等が理解できる内容。
イ 宮家邦彦、「『ネットアセスメント』に注目せよ」産経新聞(2015年6月11日)
→ 日本として戦略を立てるにあたっては、ネットアセスメントが必要であると言及。
ウ 笹川平和財団安全保障研究グループ「ネットアセスメント導入」2018年度事業(小原凡司)
→ 2021年度が当該事業の最終年度であるため、シンクタンクによる結果が待たれるところ。
エ 藤和彦、「中国「主動的な戦争設計への転換」宣言-日本、有事に備え「ネットアセスメント」強化が急務」、独立行政法人経済産業研究所(RIETI)
→ 米中対立について、主に経済的視点からどのように評価すべきかに関する内容。
オ 岩崎茂、「イージス・アショアの導入中止にあたって考えるアセスメント手法の活用」、2020年7月28日
→ ネットアセスメントという、総合的な評価により、限られた予算で効率的な防衛戦略の見直しが必要と主張。
カ 東京財団「2030年の中国の軍事力と日米同盟-米シンクタンクの戦略的分析と評価」2013.5.23
→ 討議主体の内容であり、(3)に示すカーネギー国際平和財団が出した資料を基に、中国に対する戦略的ネットアセスメントを説明。
(2)「第4章 ネットアセスメントの誕生」、アンドリュー・クレピネヴィッチ、バリー・ワッツ『帝国の参謀-アンドリュー・マーシャルと米国の軍事戦略』日経BP社、2016年4月19日、p141-176
→ アンドリュー・マーシャルの伝記ではあるものの、ネットアセスメントの必要性、その分析方法等を知る上で重要な内容。
(3)カーネギー財団「2030年における中国軍と日米同盟:戦略的ネットアセスメント」(PPT資料)、2013年5月23日
→ 米国としてではなく、シンクタンクとしてシナリオ・プランニング手法を用い、分析している。
3 主な意見交換
〇 空自も当然ながらネットアセスメントには興味を持っている。米国にあっては、マーシャルの伝記に記載されていたとおり、軍種の利害に捉われず、また誰の忖度も無く国防長官にのみに対して診断結果を報告する等、学ぶべきことが多々ある。
〇米国の関連予算は年間数億ドルと言われている。それぞれの分野の専門家を招聘し情報収集し、時に国家の意思決定者に対して、厳しい結果を提示する必要もある。
〇 ネットアセスメントについては、戦略策定において一丁目一番地という認識。空自の中での体制は、シンクタンクとしての独立性を考えると、は研研究センターが実施するのが良いのではないだろうか。
〇不確実性の時代において長期的な戦略見積りは難しい。見積り業務に従事する要員の配置期間が2年程度では分析は困難である。米国のように、真の専門家を配置することが必要であろう。
〇ネットアセスメントは、評価結果を出して終わりではなく、レビューをして見直していくことが大事である。我が国の場合、策定した戦略等の成果物を必要に応じて見直すとしているが、現実には難しいところがあるようだ。
〇 ネットアセスメントにおいて、診断という行為が重要であることを理解できた。その診断を行うにあたっては、リニアな見方による弊害については、変えていかねばならない。
〇診断上の大切な点は2つある。一つは、自衛隊の任務遂行能力を、如何なる見方でどのように評価するのかである。2つ目として、第三者的立場で専門的な知識を持った者による分析・評価の積み上げが必要である。今までは全て現役で解決しようとしていたが、不足の感があるならばOBやシンクタンクを使う時代に来ている。
〇分析に必要な膨大なデータの必要性は重要である。この場合、AI が有効に機能するものと思料するが、そのためのデータ・サイエンティストの確保・養成も必須。データから何を求めるかの空自のニーズ、それを現実に構築する為のデータ・エンジニアリング、分析スキルとしてのデータ・サイエンティストの連携が鍵。
〇ネットアセスメントのアウトプットについては、殆ど見ることができず、疑問が残る傾向が強い。つまり、受け手の取り方によってアウトプットのあり方は変わるということである。この点に関しては、ラストウォーリアにおけるソ連に対する分析を統計から考えたとの下りが大いに参考となる。
〇ラストウォーリアがマーシャルの自伝とは言いながら、示唆に富む多くのポイントが記載されていると思う。これを踏まえて空自向けのコメントが3つ。1点目は、長期的な戦力見積り等については空幕長が問を出し、これに研究センターが回答する。2点目として、ネットアセスメントに特化した人材育成・確保が大切。3つ目は、人材のまとめ役。この点では、OB の活用もあるだろう。