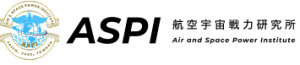Ⅰ 「昭和」からのメッセージ
1989年空幕が指揮官教育の充実施策の一環として編集した参考資料「言い残すべきこと」(ー若き指揮官達のためにー)の中から、任意に抽出した指揮に関する題材(論題)の一つを記載。
前回の続き。先人の4項目目となる「隊員指導の参考」の37の細部項目について少しずつ掲載していく中で、今回は、(5)命令と服従です。
時代の相違はあるものの、現代の指揮統率に参考となるものが少なくない。通読してもらい、自らの見解をまとめることに役立てていただきたい。
4 隊員指導の参考
(5)命令と服従
ア 戦場における軍紀の欠如は死と敗北を意味する。ドイツ人が多くの戦乱を生き延びてきたのも軍紀の維持の賜物にほかならない。(パットン米陸軍大将)
イ 上司の命令指示には機敏に反応せよ。
ウ 自信過剰の者は、上司の命令や指示を早呑み込みしたり、注意等を聞き流す傾向があるものだ。各自心せよ。
エ 命令の誤認による不服従は、責任を免れることはできない。
オ 緊急対処時には命ぜられたことを直ちに実行せよ。命令の適法性に疑問があれば、実行してから後に申し出よ。緊急時に法令問答をやっている余裕はないのだ。
カ 適法性が明確でない命令には従わなければならない。
キ 納得できないと言う理由で上司の命令を拒否することはできない。
ク 規律を守ることは、所属する集団に対する、成員としての義務である。
ケ 個人的な好みで上司に仕える人間になってはならない。どんな上司にも誠意をもって仕えることのできる人間たれ。
コ なにびとも、人に従うことのできるものでなければ、人を従わせることはできない。
サ 積極的に己の是と信ずるところを意見具申し、決定されたことには、たとえ意見を異にしたとしても、潔く従え。
シ 意見具申は、指揮官の決心以前に行われるべきである。指揮官の決心が明確なときは、部下は実行あるのみである。
ス 指揮官の自由裁量権に支障をきたすような意見具申や言動は厳に慎むべし。
セ 幕僚や部下は指揮官の意向を誘導するな。客観的判断資料の提供に努めよ。
ソ 「〇〇してくれないか」、「〇〇してはどうか」と上司に穏やかに言われても、それは命令と受け止め実行せよ。
タ 上司から何気なく言われたことでも、聞き流すな。命令・指示であることもある。
Ⅱ 「平成」からのコメント等:
ここではⅠ項の大項目及びその内容を受けて、私(福江)が現役時代に思考及び実行した体験を基に、コメントしたもの。令和の現代にあって、指揮統率における不変の部分、そして変化すべき部分があるはずである。令和の時代で服務する皆さんの参考になれば幸いである。以下の文中、「先人」とあるのは、Ⅰ項の論者を指している。
「命令」「意見具申」について
ここでの先人の命令等に関する意見は、防衛行動、作戦運用の状況下を意識し、指揮実行上の原則を自らの言葉で強調されている印象を受ける。指揮の本質という点で理解できる。
ただし、各級指揮官は、いかなる状況下にあっても、適法性・合法性を欠いた命令・指示を下してはならない。受令者の立場にあっては、違法性の有無を精査する慎重さも必要である。
私の現役時代における関連の業務経験を一例として示す。
空幕勤務時、上司から航空機の仕様変更に関する指示を受けた。その内容を担当部署の幕僚と検討したところ、その実行には法的手続きを執る必要があることがわかった。その一貫で業務計画に反映した上で相当額の予算を取得しなければならないことも明らかになった。
上司がこの案件にかなり執心で、かつすみやかに実現させたいとの意志を持つことも理解していたので、実行を決心され関係部隊等に命ずることになる前に、直近の幕僚である私が意見具申を行うこととした。
信頼する上司に仕える一幕僚として、上司の指示に抗い、服従しないという状況を生起させぬよう配慮しながら、案件を事業として成就するための算段を明確に伝え、併せて専門幕僚及び部隊指揮官等、関与する関係者の意見及び具体的なデータを付言した。
結果として、私の不服従的な(と思われたかもしれない)行為に対して厳しいご指導をいただいたが、その案件は命令となって即実行という事態には至らなかった。また、その後も再燃することはなかった。
この事例から、私は幕僚(受令者)として意見具申の重要性及び困難性を、身をもって認識するとともに、指揮官の立場で命令・指示を下すにあたっては、事前に適法の確認を怠ってはならないことを学ぶこととなった。
私の経験は、平時における防衛力整備上の業務処理案件であったが、有事において時間的猶予のない中での命令であっても、違法性を理解しない、あるいは違法性を知りつつ、指揮を実行することは決してあってはならない。そのために、空自は平素からあらゆる作戦行動を細部に至るまで検証する等して、有事法制のさらなる充実に努めるべきである。
以下は、空自教範からの一部抜粋で、「命令」「意見具申」にかかる参考です。
教範「指揮運用綱要」の「第1章 指揮 8命令」
指揮官は、決心に基づき適時適切に命令を発しなければならない。命令には、発令者の企図及び受令者の任務を明確に示し、状況及び受令者の性質と知識・技能に適応させることが必要である。この際、受令者が自ら処断できる事項については、みだりにこれを拘束してはならない。
また、命令は、その内容及び状況に応じて下達法を適切にし、時機を失することなく受令者に迅速確実に到達させることが重要である。
教範「指揮運運用綱要」の「第1章 指揮 12意見具申」
指揮官は、上級指揮官の指揮に資するため、状況に応じて積極的に意見を具申することが必要である。
意見具申は、部隊全般の任務遂行に貢献することを主眼として、常に大局的見地に立ち、かつ、機宜に適する方法で行わなければならない。たとえ意見が入れられなかった場合においても、謙虚、かつ、誠実に上級指揮官の意図の具現に最善を尽くさなければならない。