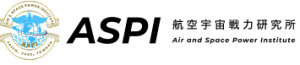1 郷土の特攻史を知るきっかけ
一昨年、『特別攻撃隊全史』(以下、全史)の第2版が12年ぶりに刊行された。当会に入会して4年目ながら、その記載内容を一部改訂する事務にかかわった。全史を精読したのは、正直このときが初めてだった。
印刷会社の校正刷りを原稿と照合する作業は、時間と根気を要した。しかし、おかげで私の郷里が特攻史に関わりを持つことに、気づくことができた。該当箇所は、全史の332頁。鹿屋特攻基地の碑「特攻隊戦没者慰霊塔」に関する説明の一部、「…出撃した神剣隊(大村空)…」の記述文まで読み進んだところで、思わず手を止めた。
私の出身地である長崎県大村市が前大戦中、戦火に見舞われたことは幼い頃から知っていたが、特攻に纏わる話を耳にしたことは一度もなかった。当時、市内に配置されていた大村海軍航空隊において、航空特攻の部隊が編成され出撃した史実があったとは驚きだった。
全史を改訂する作業を再開した時には、郷土の特攻史を調べてみようと思い立っていた。
先述の作業から数日後だったと思う。母校(県立大村高等学校)の一年後輩にあたる山下健一郎氏(現・大村市の副市長)が公務のため上京した折に、私の勤務先を訪ねてくれた。久しぶりの再会だった。その際に当会の名刺を渡したことが、郷土の特攻史に関する調査を進めるきっかけとなる。
後日、大村市立図書館職員の方から、航空特攻の部隊である「神剣隊」に関する情報が私の元に寄せられた。山下副市長が特攻にかかる郷土史の有無について、問い合わせてくれたのである。
2 郷土の歴史資料館の協力を得て調査開始
郷土の図書館からの情報提供は、当会の理事として思案中であった課題の解決策にもなった。私は調査研究グループの長に就いたばかりで、その業務の方向性を定めなければならない立場にあった。当該グループ員は私を入れて7名。専従できる会員は一人もおらず、当会が独力で特攻にかかる新たな史実の発見や保管データの検証を行うことは、かなり難しい状況にあった。
その最中に、先述の「でき事」に出会ったわけである。全国各地に所在する歴史資料館、図書館等との共同作業ならば、より迅速にして精度の高い調査研究を行えるとの期待が一気に高まった。潜在的な史実が明らかになる可能性すら予期できた。
こうした思いを持って、大村市歴史資料館・学芸員の川内彩歌氏に協力の依頼をしたところ、「自治体としても大村の歴史研究に繋がることから、情報提供を惜しまない」との返答であった。これにより、郷里の歴史資料館とコラボしながら特攻の調査研究を行い、その一連の活動と成果を当会の会報に掲載しようと考えるに至った。
今回の調査に関する詳細な経緯や結果は後述するとして、主な成果(私が初めて知り得たことを含む)については、次の5つになる。
- 6次にわたる航空特攻の「神剣隊」搭乗員は、大村航空隊において訓練し編成され、鹿児島県の鹿屋航空隊に移動後、鹿屋基地から出撃したこと。
- 「第3神剣隊」の搭乗員であった甲飛4期の林田貞一郎氏については、訓練期間中に懇意にしていた大村市民がいたこと。
- その市民の親族が、戦後に同氏の生前の写真を知覧特攻平和会館に出向いて寄贈していたこと。
- 前項の写真について調査する中で、鹿屋航空基地史料館にも問い合わせたところ、保管資料から林田氏の辞世の句を知ることができたこと。
- 「神剣隊」とは別に、特攻戦没者の中に大村市出身の方が2名おられたこと。おひとりは航空特攻部隊「七生隊」の出撃で散華。もうひとりの方は、呉工廠において戦死されていること。
いずれも新たな史実の発見とまでは言えないかもしれない。しかし、戦後70年以上が経過し、郷里において特攻隊員と一般市民がふれあった事実が消失しかける中、関係者の記憶を留め置くことには大きな意義がある。
これまで多くの人に知られなかった特攻隊員個々の短い人生を明らかにすることは、慰霊にあたっての重要な行為である。
3 大村が軍都と呼ばれた所以
(1)地名の由来
大村の地は、日本初のキリシタン大名である大村純忠(大村家第18代)や天正遣欧少年使節等で歴史的に知られている。江戸時代の270余年の間、12代にわたる大村氏がこの地を統治していた。
ちなみに、藩主の居城であった玖島城の跡地は、現代では大村公園と呼ばれる都市公園となっている。日本の歴史公園百選のほか、桜の名所百選にも選定されている。
地名の由来については、古文書『大村家記二』に「大村トハ当郡中ニ於テ土地肥良広大ナル村ナリ所以ニ大キ成ル村ト呼始シヨリ遂ニ村号トス」(大村とは、田畑が広大な地域という意味であり、彼杵郡内で一番広大な農耕地であったため、大きなる村と呼び始めた)と記されている。
(2)軍都としての発展の歴史
大村で市制が施行されたのは、昭和17年2月11日。1町5村の合併によっている。つまり大村市の誕生は、前大戦の開戦直後になる。
大村市のホームページ中にある『新編大村市史』(以下、市史)には、当時の大村が昭和初期から戦時体制へ移行する日本各地の社会動向をうかがいながら、自らの都市計画を立案し、実行していった経緯が詳しく記されている。
その一つに、第21海軍航空廠が昭和16年10月に設置されたことを取り上げている。これにより、昭和17年末における大村市の人口は同廠の拡張もあって約5万6千人に、翌年には約6万8千人に激増している。明治以降、大村に順次設置された後述する陸海軍部隊に加え、この海軍航空廠の新設・拡充に伴った市政運営及び都市計画が進められた結果、大村市は軍都を形成していった。
なお、市史には「軍都」について、次のような付記がある。「軍都という言葉自体に明確な定義はなく、各個人の所見に従って呼称される場合が大半である。これらのことは大村と同様に陸軍ないし海軍が常駐していた全国の自治体や地域においても同様で「軍都」や「軍郷」といった言葉を研究者・執筆者それぞれが独自に使用しているケースや使用しないケースを見ることができる」。
(3)前大戦中の大村に所在した旧陸海軍部隊
大村海軍航空隊は、大正11年12月に開隊している。当初、西日本における操縦者の基礎訓練から実用機慣熟訓練までの一貫した教育を目的とした地名冠称の海軍航空隊であった。
前大戦の後半になると、戦闘機隊の教官を中心に防空任務を担当するようになり、末期においては航空特攻を遂行する部隊となる。
大村には、大村海軍航空隊のほかにも、いくつかの航空隊が作戦推移に応じて編成、配備されていた。それらの戦闘機部隊による「戦闘詳報」、民間団体による「管内主要都市空襲被害状況」、警防団長による日記等の貴重な史料も市史に記載されている。
特に、昭和19年8月開隊した352海軍航空隊(草薙部隊)及び海軍最後の精強部隊と言われた343海軍航空隊が大村海軍航空隊と協同して北九州方面の防空等にあたっていた詳細な記録が目を引く。
352海軍航空隊は、昭和20年8月9日長崎に原爆が投下された際、その上空まで進出して最初に航空偵察した航空部隊でもある。なお、三桁冠称の海軍航空隊のうち、300番台は戦闘航空隊を示している。
一方、陸軍部隊については、陸軍歩兵第46連隊が明治30年から昭和20年終戦までの間、大村の地に駐屯していた。この連隊を母隊として編成された多くの連隊が、大村を拠点として各地で活躍した記録が残されている。
詳細については、郷土出身の村井敏郎氏によって編纂された『郷土部隊50年の足跡 大村陸軍 』(昭和58年8月発行)をご覧いただきたい。
この著書は、防衛庁戦史室(当時)の戦史叢書や戦闘体験者からの証言に基づいている。大村で編成された多くの陸軍部隊が、どのように行動し活躍したかを戦跡を追いながら、わかりやすくまとめられている。
4.大村の地に関わる特別攻撃隊
(1)航空特攻「神剣隊」の存在
昭和20年米軍が沖縄に上陸した以降、日本の陸海軍は特攻化へ向けた動きを先鋭化させていく。連合艦隊司令部は、残存艦艇(戦艦大和を含む)及び残存航空機の総特攻を企図する菊水作戦を展開することとなる。
こうした全般の戦況下にあって、大村海軍航空隊においても操縦の練成訓練を終えた特攻隊員が、部隊名「神剣隊」として編成される。
「神剣隊」は菊水作戦の遂行中に6個隊が編成され、その後に鹿屋基地に移動、沖縄方面に向けて出撃している。しかし、大村海軍航空隊は戦局により菊水作戦半ばにおいて解隊(昭和19年5月5日)されている。このため、「第6神剣隊」は、721海軍航空隊に編入された後、鹿児島県の鹿屋基地から出撃している。
「神剣隊」については、大村市歴史資料館から、次の一文と出撃関連資料(①~⑥の部隊毎に、出撃数等、参加作戦、出撃日の順で記載)を提供していただいた。
「全国各地から集まった特攻志願者は大村海軍航空隊において訓練。その終了後に、特攻部隊となる「神剣隊」として編成され、鹿屋航空隊に移動した後、沖縄周辺へ出撃した。昭和20年4月6日から5月11日の間に、「神剣隊」の6個隊が編成され、計48人が散華」。
①第1神剣隊(大村航空隊):出撃機数16機に対して未帰還16名 菊水1号作戦 昭和20年4月6日
②第2神剣隊(大村航空隊):出撃数9機に対して未帰還9名 菊水2号作戦 昭和20年4月14日
③第3神剣隊(大村航空隊):出撃機数不明(*)の中、未帰還3名 菊水3号作戦 昭和20年4月16日 *…同日、出撃した特攻部隊は3個隊(第2昭和隊、第3七生隊、第3神剣隊)、その総機数が20機で神剣隊のみの機数は不明)
④第4神剣隊(大村航空隊):出撃機数4機に対して未帰還1名 菊水3号作戦 昭和20年4月16日
⑤第5神剣隊(大村航空隊):出撃機数20機に対して未帰還15名 菊水5号作戦 昭和20年5月4日
⑥第6神剣隊(戦闘306飛行隊):出撃機数4機に対して未帰還4名 菊水6号作戦 昭和20年5月11日
なお、上記のカッコ内に記された「大村航空隊」は「大村海軍航空隊」を示している。「第6神剣隊」の所属が戦闘306飛行隊となった背景については、(3)項の「桜花」等による航空特攻との関係において記述する。
(2)掩護戦闘機と「神剣隊」の関係
市史を読み進めていくと、大村に配備された戦闘機による特攻機の掩護及び制空戦闘の状況についての記述があった。これ自体は、防衛省防衛研究所に所蔵されている『笠野原基地戦闘詳報』に基づく内容である。また、国立公文書館・アジア歴史資料センターのデータ・ベース検索でも閲覧できる。
笠野原基地は、鹿児島県鹿屋市に配備されていた笠野原海軍航空基地である。当該戦闘詳報によると、菊水1号作戦が実施される中、先述した352航空隊、大村海軍航空隊、元山航空隊所属の零戦等が笠野原基地まで進出した上で、徳之島、奄美大島、種子島、沖縄北端に至る空域での制空任務に従事している。
これら掩護戦闘機も甚大な被害を受けている様が記されている。「第1神剣隊」が出撃した4月6日付の記録は、次のとおりである。「第4波として笠野原基地を1420に発進した零戦23機のうち、1915までに帰着したのは11機、未帰還は指揮官機を含む7機。他の5機については、エンジン不調、交戦等により徳之島、喜界島、種子島に不時着」と記録されている。
航空特攻以外においても、大村に関連する航空隊に所属する多数の戦闘機操縦者が作戦遂行のために還らぬ人となったことが偲ばれてならない。
(3)第721海軍航空隊と「神剣隊」との関係
(1)項で述べた「第6神剣隊」が編入された721海軍航空隊が開隊したのは、昭和19年10月1日。原隊は、茨城県の百里原航空基地(現在の航空自衛隊百里基地)である。700番台の冠称番号は、陸攻航空隊を示している。
当該航空隊は、攻撃708飛行隊、攻撃711飛行隊、戦闘306飛行隊、戦闘307飛行隊から編成されていたことから、「第6神剣隊」は隷下の戦闘306飛行隊に編成替えとなったものと思われる。
721海軍航空隊は、1式陸攻に「桜花」を搭載して米軍艦艇に体当たり特攻を支援する航空隊で、「神雷部隊」と称されていた。
その第1陣となった第1神風桜花特別攻撃隊神雷部隊については、20年3月21日陸攻18機及び零戦19機等が出撃、全機未帰還となった。160名が散華されている。その後6月22日の第10次まで神雷部隊による特攻は継続され、1式陸攻だけでも計79機が出撃し55機が未帰還となっている。
細部は、加藤浩「神雷・竜巻部隊概史」「人間爆弾と呼ばれて 証言・桜花特攻」(文藝春秋、2005年3月25日)をご覧いただきたい。
5.地元住民と特攻隊員のふれあい
調査活動の中で、「神剣隊」に関係する文献、証言記録等を収集していたところ、意外にも親族から「第3神剣隊」の隊員に関する情報が得られた。
以下は、同隊の搭乗員が鹿屋基地に進出するまでの期間、妻の祖母が食事をふるまう等、もてなしていた様子を、妻が義母から聞き取った内容を基に記述したものである。
(1)昭和20年春
特攻隊員とのふれあいを祖母が持つようになった時期、経緯や依頼主についてはわからない。昭和20年桜の開花前からの出会いがあったようである。
その時期、週末になると4~5人の特攻隊員が祖母の家に食事に来ていたことを当時7歳であった義母が覚えていた。祖母の家は大村市内の竹松という地域にあり、大村海軍航空隊に近い場所にあった。
その中の一人が、林田 貞一郎(熊本・天草出身 甲飛4期(「神剣隊」搭乗員等の集合写真のうち、前から三列目の右から2人目)氏である。彼は、菊水3号作戦において「第3神剣隊」搭乗者として鹿屋基地から那覇湾の敵艦船攻撃に出撃し、昭和20年4月16日に戦死している。当該隊員については、全史の195頁に記載がある。
同氏は、祖母を母のように慕い、義母を妹のように可愛がっていたと聞く。出撃日が近くなった桜の時期に、義母は隊員達から「散る桜 残る桜も 散る桜」の句を、何度も教えられ暗唱するまでになったとのこと。その様子を見て林田氏が微笑む中、祖母は涙していたそうだ。
鹿屋基地への進出直前に林田氏等が祖母の自宅を訪問した際のエピソードがある。分隊士の林田氏が、航空事故で負った火傷のため大きく開けられない口で、同行隊員の分までタバコに火をつけて渡し、自らもそのたばこを吸っていた姿が忘れられないと義母は言う。
鹿屋基地へ進出する当日には、林田氏が搭乗した戦闘機が祖母の家の直上を数度旋回したことも義母は覚えていた。その時には、林田氏の実父が彼の郷里である熊本から来られており、祖母や義母と一緒に家の洗濯干し場で大きく手を振って見送られたそうである。
こうした家庭的な交流を持つ間、祖母は林田氏をはじめ特攻隊員の写真を撮り、その裏に日時や名前と共にメモを残していた。この行為から、祖母は彼らの任務は必死であることを理解していたことがうかがえる。
林田氏にかぎらず特攻隊員の戦死の知らせが、どこからか届くたびに、祖母は彼らの遺品をまとめて実家等に送っていたとのこと。戦死通知は軍にとって伏せておきたい情報であるはずだが、なぜ祖母に伝えられたのかは不明なままである。
(2)平成15年1月
祖母が昭和45年に他界するまで林田氏の弔いとして続けていた事があったと祖母の孫にあたる私の妻が語ってくれた。祖母は、林田氏の月命日に必ず仏壇に手造りの「おはぎ」を供えていたとのことだ。それは、林田氏から「もし自分が戦死したら、大好きなおはぎを命日に供えてほしい」と頼まれていたからだと祖母がある日、妻に話してくれたそうである。
平成15年になって、義母の長男が母親を連れて鹿児島を旅行することを申し出た際、義母は旅行に合わせて特攻隊関連の歴史資料館を訪問することを希望したそうだ。それは、林田氏を中心に撮った写真(祖母による裏書きあり)が唯一手元に残っていたため、供養になればとの思いがあったからである。
義母と長男は、同年1月16日に知覧特攻平和会館を訪れている。なぜ林田氏が出撃した鹿屋基地に隣接する鹿屋航空基地史料館が訪問先にならなかったのか。このことを確認したところ、林田氏の出撃基地が鹿児島方面だったという記憶と、それならば知覧にある特攻平和会館ではないかとの思い込みがあったとのこと。結果として、当該写真を同会館に寄贈し帰省している。
(3)令和3年12月
今回の一連の調査では、妻の祖母が知覧特攻平和会館に寄贈した写真の存在を確かめることが重要なポイントの一つとなった。これまで関係者による生前の特攻隊員に関する単なる記憶であったものが、物証を得ることで確か
な証言になるからだ。
私と妻は事前に入館の予約を取った上で、令和3年12月7日知覧特攻平和会館を訪問。同館学芸員・八巻聡氏に対応していただき、義母が寄贈した写真の写し(寄贈写真そのものは所在がわからず)をコピーしたものを受け取ることができた。
まず、写真の中央(大人列の右から三番目)が、林田貞一郎氏。一番左が妻の祖母で、子供は義母である。なお、大人列の一番右は「眞砂上飛曹」、右から二番目は「小田部久左衛門」、祖母の右側の女性は「郁子さん」と裏書きされている以外、詳細は不明である。
肝心の裏書きについては、写真を貼っていた糊痕のために一部判読できないが、以下の事が記述されている。これは祖母の直筆である。判読困難な部分は*印を付けた。
『昭和20年4月8日写
林田貞一郎分隊士、特攻隊として沖縄に出陣 12日出発。4月16日見事敵艦に命中、24才の若櫻花と散りけり。 林田の兄ちゃん 忘れがたき修養せし人
ニックネーム 坊やノ人*
眞砂上ヒ曹(***)、小田部久左衛門(**)、**一家の*人だった。****郁子さん、綾子***ので、林田の兄ちゃんの意志を忘れず***張りませう』
林田氏が鹿屋基地から出撃する4日前の写真からは、様々な事を想像してしまう。林田氏だけが搭乗前の飛行服をなぜ着用していたのか、微笑んでいるようにも見えるのはどうしてか、そしてどのような心境だったのか。
甲飛4期で分隊士となれば熟練の操縦者であっただろうになぜ志願したのだろうか、それは顔の火傷と何か関係があるのか。大村海軍航空隊では分隊士兼ねて教官が多かったとの記録もあることから、教え子に対するなんらかの思いがあったのではないだろうかと。
ちなみに、知覧特攻平和会館内において紹介されている電子版の隊員情報には、この写真から本人の顔だけを拡大したものが掲載されている。
翌日12月8日早朝に鹿児島市内を出発し、鹿屋航空基地史料館に向かった。同資料館では、研修教育等担当の山森正彦氏に出迎えていただき、林田氏にかかわる一連の資料を拝見させてもらった。ここでは、平成7年9月に遺族の方が寄贈された林田氏の遺影と熊本にある林田氏の墓石に刻まれている辞世の句(下記のとおり)をそれぞれ写しでいただくことができた。
『敷島の大和男児が腕を撫し 嗚呼待ちたるぞ今日の出陣 いざさらば桜と共に吾は征く 御国を護る靖国の宮』
この時の鹿児島における調査活動は、私はもとより妻にとっても感慨深いものであったようだ。妻にしてみると、戦時中における祖母の生き様の一端を知ることができたとともに、特攻隊隊員の生前の姿をうかがい知ることで特攻に関する理解を深めることができたのではないだろうか。
6.大村出身の特攻隊員に関する調査とその結果等
先述の「神剣隊」戦没者については、全史における出身県を調べた限りでは長崎県の記載はない。このことを知った時に、大村市の出身で特攻隊戦没者の方がおられたのかについて、併せて調べることを思いつく。大村市歴史資料館に問い合わせたところ、これまでに大村出身の特攻隊員をテーマにした文献はないとのことであった。
その際、同資料館からは長崎県下及び大村市の戦没者名簿から記録をたどることは可能ではないかとの提案をいただいた。
そこで、同資料館から紹介してもらった2冊の図書(戦没者名の記載あり)と、全史第2編・特別攻撃隊戦没者名簿を照合することにした。
紹介図書の一つは、『風雪の塔』という長崎県連合遺族会発行の図書で、同会の創立25周年を記念した製作された特集(昭和47年7月)号である。もう一つは、『ふりむいて』という大村市遺族会が戦後50周年記念誌として発行(平成7年8月11日)したものである。ただし、この図書は、明治10年西南の役以降、大東亜戦争に至るまでの戦没者及び遺族を対象とした名簿になっている。
これら3冊を照合した結果、2名(①少尉・晦日 進 ②兵曹長・深江 正市)の方が該当することがわかった。ご両名にかかる情報を整理した結果は、次のとおりである。
①晦日 進 氏:全史の該当頁は198頁。「海軍航空特別攻撃隊・第5七生隊、昭和20年4月29日、沖縄島北端120度60海里にて戦死」との記載あり。紹介図書に記載された戦死場所、戦死年月日、年齢と一致するほか、海軍大尉への昇進、勲5等双光旭日章の受章と実家の住所等が明記されている。
②深江 正市 氏:全史の該当頁は234頁。「特殊潜航艇・日本本土西部、昭和20年6月22日、呉工廠にて戦死」との記載あり。また紹介図書には戦死場所「内地」及び実家の住所との記載のほか、戦死年月日が昭和20年7月22日とある。
この照合結果から、①晦日氏は、記載事項の全てが一致することから確定してよいと考える一方、②深江氏については、戦死日がちょうど1か月異なるため、同一人物と認定することは現時点では難しい。ただし、呉工廠造兵部が空襲されたのは、昭和20年6月22日であることは事実である。
7.各地の歴史資料館等と連携して得られる特攻史の成果等
(1)調査の総括
私の郷里である大村市歴史資料館から届いた1本のメールを皮切りに、大村市にかかわる特攻史を調べることになった。当該資料館の全面的な協力が得られたことで、設定した調査を順調に進めことができた。ここであらためて明らかにできた事項といまだ不明な事項等について総括する。
ア 海軍航空特別攻撃隊にうち、6次にわたる神剣隊は、大村市内に所在した大村海軍航空隊において訓練、編成された。ただし、第6神剣隊に関しては、大村海軍航空隊が5月5日に解隊されため、出撃前に721海軍航空隊に編成替えとなった。
なお、大村海軍航空隊跡地に戦後建設された陸上自衛隊竹松駐屯地において、現地取材を行った際に、同駐屯地・勤務隊員の協力によって、6頁に掲載した「神剣隊」の集合写真が撮影された場所をほぼ特定することができた。
イ 神剣隊の搭乗員達が鹿屋基地に移動するまで滞在していた大村の地において、週末に航空基地周辺の住民と交流があったことが地元関係者からの聞き取りにより、その一部を明らかにすることができた。
特に、戦後も地元住民が保管していた第3神剣隊の分隊士として出撃した甲飛4期の林田貞一郎氏等の写真は貴重な記録であった。その写真自体は、私の親族により平成15年1月に知覧特攻平和会館に直接届けられ、現在も同資料館に保管されている。遺影として掲示されていることもわかった。
ウ 前項の関連で、当初海軍の航空特攻であれば、義母等は鹿屋航空基地史料館に写真を寄贈したと判断したため、同館に調査を依頼。しかし、この判断は誤りであったが、平成7年に林田氏の実弟と従弟が同館に遺影を寄贈されたことを知ることができた。その際、林田氏の墓石に刻まれた辞世の句を確認できた。
エ 全史に記載されている特攻戦没者名簿と大村遺族会名簿を突合することで、特攻戦没者の中に大村市出身者2名がおられることを確かめることができた。晦日進氏は、海軍航空特別攻撃隊・第5七生隊の出撃(昭和20年4月29日)で散華されたことがわかった。
深江正市氏については、特殊潜航艇関連で呉工廠において戦死されている。しかし、戦死日に関して、全史では昭和20年6月22日とある一方、遺族会図書には同年7月22日と記され異なっている。
なお、戦死日の異なる点については明らかにできなかった。
(2)各地の歴史資料館等との連携による特攻史の調査研究に寄せる期待
近年、当会の調査研究グループ(現在員7名)は、ほぼ単独で調査命題を設定した上で成果を求める地道な作業を行ってきた。この作業要領はかなりの時間と労力を要し担当会員個人の負担が大きい。その上に、今後は特攻隊戦没者遺族からの直接的な協力が得難く、潜在すると思われる貴重な特攻隊関連資料を入手する可能性はますます低くなる。
こうした中、今回は期せずして、地方の歴史資料館・学芸員等の積極的な協力支援が得られたことで調査を進める機会に恵まれた。これまで知られていなかった点及び不明確であった点を、明らかにすることができた。しかも従来の要領に比してかなり効率的であった。
今回のような地方の歴史資料館等と当会によるコラボレーションが特攻史の調査研究にもたらす効果としては、次の点が挙げられる。
ア 各地の歴史資料館等には、特攻をはじめ戦時中の記録資料が秘蔵の状態で、かなり保管されている可能性が高いこと。
イ 歴史資料館等で勤務する学芸員等の知見は高く、特攻に関しても有力な情報の提供を期待できること。
ウ 特攻史に関連する資料・データの収集並びに調査要領の検討等に費やす時間を短縮することができること。
当会の調査研究グループの長を務める者としては、まずは今回行った情報収集及び調査のやり方を一つのモデルとして確立させたい。その後は、当会独力の調査研究に加えて、地方の自治体及び歴史資料館等との連携を重視した方法により、これからも散逸し続ける特攻史にかかる貴重な記録を発掘していくことで実績を上げていくことを望んでいる。
(3)栄都へ発展した大村市の現在の姿
私が郷里で過ごした小中高生時代の昭和40年から50年初め、大村市は人口5万人で推移したが、今や10万人に達するほどの都市と呼ぶにふさわしい発展ぶりである。全国的に少子化が進む中にあって、2025年には人口10万人を目指している。
現在、園田裕史市長のもと第5次大村市総合計画が推進中である。「しあわせ実感都市大村」をスローガンに、「行きたい、働きたい、住み続けたい」を将来ビジョンのテーマに掲げ、市民と共に幸せを実感できる街づくりを取り組んでいる。
今年は、大村市にとって市制施行80周年の大きな節目の年にあたり、様々な事業が市の発展・繁栄に向けて取り進められている。中でも今秋には西九州新幹線の開業が予定されアクセス環境が良くなることで、経済効果が高まるとの期待がある。
その発展を象徴する一つに、冒頭で触れた令和元年10月に新設された「ミライon【onは全角小文字でお願いします】」がある。同施設は、長崎県立・大村市立一体型図書館と、大村市歴史資料館との複合施設である。この施設では、運営にあたって「郷土(ふるさと)の歴史と文化に親しみ」を掲げていることから、ぜひ前大戦時の苦難の歴史もテーマに取り上げていただきたい。
今回の調査結果が当会の会報に掲載されたならば、協力先である大村市歴史資料館に寄贈するとともに、「ミライon」において多くの市民の目に留まることを期待したい。
結びにあたり、大村の地を離れて半世紀近く経つ今日、特攻隊戦没者の慰霊顕彰を目的とした一連の調査活動を通じ、再び郷里に想いをはせることができたことに心から感謝したい。
特攻にかかる調査研究は、これからいっそう困難な活動となるであろう。それでも地方自治体及び各地の歴史資料館等の協力が得られれば、私自身の当該活動への取組み意欲は高まり、新たな成果を求める自信と行動力になる。次なる「身近なる特攻史」の対象となる市町村等が、この記事がもとで早期に定まることを切望する。