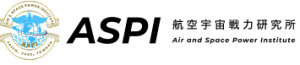第6話 戦略と戦略的思考
戦略と戦術は、この一年間諸君が学ぶテーマであるし、将来に亘って究明すべきテーマであるから、手短かに講話するような話題でないとも言える。しかし、逆に私自身が考えて来たことを、一言で言えと言われれば、それを一言で言 えなければならないことも、私の本質論で述べたところである。 したがって今回は、戦略と戦術の内、戦略について私の考えを諸君にぶっつけて、君達自身の戦略を構築する肥やしにしてもらいたいと思う。 先日の戦略応用研究発表において、ある発表者は次のように述べていた。脅威は、意図と能力から成る。この意図は不定不明であるので、我が戦略を策定するに当たっては、能力を主体に検討するという発言の下に、縷々述べていた。この考え方に即して、能力をもって何が出来るかを考えてそれに対応する我が方策を案ずればよいというものである。昨今、多くの立論がこの手法で語られている。果たしてそれでよいのか。 戦略とは何か。私の結論は、戦略とは味方を増やし、敵を減らす謀りごとのことである。戦略とは、戦いの謀りごとである。戦いとは、相手を叩くことである。個人の場合から国のレベルまで、戦いは相手との叩き合いである。戦争の場合は、国と国の叩き合いである。これを謀るのである。謀るとは、敵味方の目方を比べることである。比べてどちらに分があるかを見ることである。分とは勝ち目を言い、味方に勝ち目があるようにすることを策することが、謀りごとを為すということの意義である。 その方策とは何か。自国に分があるようにするには、二つの方策がある。 第一は、味方の分を増すこと、即ち連合して当たること、第二は、敵の分を減ずること、即ち敵を分断して少なくすることである。これを案ずることが戦略であり、そういう考え方を採ることが戦略的な思考というのである。ここまでは、戦略論の第一段階である。ではどうすれば味方が増え、敵方が減ずるか。 これを知ることが戦略の第2段階であるp私の考えは、戦いは一言で言えば、「利と理」の追求である。ひらたく言えば「何々を欲しい、何々がしたい」。以前本質論で述べた手法でいえば、戦争の本質は、その目的に存し、その目的とは、 「利と理」の追求である。 利とは利益であり、それを得ることによって得る物質的益である。理とは、道理の理であって、戦いの大義と言われるものである。一般には、利と理が一致することが通常である。しかし大義と言われる理は、表向きであってその裏には、表裏一体としての利が存する。むしろ利のために理を合わせるということさえ希有ではない。しかし常に理は表面である。 戦略を策し、味方を増やすためには、第一には、理で味方を説得し、その理の裏にある利を知らしめ我々に寄することによって、その利が得られることを承知させることが必要である。更には、利をもって敵方を味方にすることができる。その場合も同時に理を抱き合わせにすると更に効果的である。 戦略の話を具体的な事例を用いずに話したので、やや抽象論に過ぎたが、こ れを、今回の湾岸戦争に当てはめてみてほしい。この私の戦略論の立場から、湾岸戦争を戦略的思考で論究した多くの論文のうち、日本にとっての湾岸戦争の理と利を、明解に説いたものに、中央公論平成3年4月号の堺屋太一論文がある。我が国の戦略研究のーつのモデルとして、諸君も是非参考にしてほしい。 ここで、もう一度最初に述べた諸君の戦略応用研究の発表における脅威の研究のうち、意図の分析についての疑問に戻ろう。戦略とは戦いの謀りごとであり、その内容は、味方を増やし、敵を減ずる方策を立てることであると述べた。 その方策の中心は、理と利をもって、味方につけ敵をつきくずすことである。それは、正に相手の意図を詮索することに他ならない。結論を言えば意図を詮索することが戦略なのである。逆に言えば、意図を抜きにした戦略論は、戦略論でなくなると言える。 我々は、この意図の研究が現実的で生ぐさく、差し障りが多いが故に、複雑で、流動的で、かつ多様な見方ができて、主観的になり、客観性が疑問視されるが故に、避けて通り易い。しかし、避けては通れないのがこの戦略論の本質である。我々は、より客観的、普遍的なる我が国の活路を軍事専門家として提言しなければならない。それは我々の責務でもある。諸君宣しく戦略を学び、立案し、提言して、我が国を安泰ならしめよ。
第6話に想う(記 福江広明)
戦略という言葉を強く意識したのは、指揮幕僚課程(CSC)の入校(平成2年度夏)時だった。
今回のコメントの参考にしようと、久しぶりに入校当時のノート(ルーズリーフ用バインダー)を開いてみたところ、最初の頁に、幹部学校戦略教官室が作成した教育資料『「戦略」について』を綴じ込んでいた。その要所には、私がカラーマーキングした跡が残っている。同資料の概要は次のとおり。なお、全文は最下段に掲載。
『「戦略」という言葉には、幾つかの意味がある。中でも幹部学校で学ぶべきは、「目標達成のための手段、方策」という意味だ。“国家戦略”“軍事戦略”“防衛戦略”等がこれに該当する。この意味においても二つの捉え方がある。一つは「当該目標を達成するために、現在保有する諸力をどのように使うべきか。」という問題解決型戦略。もう一つは「当該目標を達成するために、将来を見通して今からどのような手(方策、手段)を打つべきか。」という未来志向型戦略だ。身近な例では、前者は「防衛及び警備計画」(作戦計画)であり、後者は「防衛力整備計画」等がそれに該当する。CSCで学ぶべき戦略は、もちろん後者である。』
CSCにおける戦略に関する教育は、入校から間もなく開始された。具体的には、防衛基礎Ⅱというカテゴリーにおいて、「クラウゼヴィッツの戦争論」を皮切りに戦争理論、諸国の軍事戦略の講義を経て、最終的には戦略応用研究をもって修学するよく練られたプログラムであった。
あらためてノートを見返してわかったことがある。戦略について、なんとか理解しようとしているものの、消化しきれていない部分が多分にある筆記具合であった。
しかし、CSC履修後、部隊等において実務を通じて戦略立案・作成の重みを体感し、少しずつではあったがCSC学生時の未消化部分を解消することで理論から実践力が身に付いていったように思われる。
問題解決型戦略に該当する防衛及び警備計画、大規模演習計画等については、方面隊司令部の防衛班長、空幕の運用課幕僚としての勤務時代に作成に従事。また、未来志向型戦略に当たる防衛力整備計画や長期航空防衛見積り等の作成に関しては、空幕の防衛課研究班長時代に取り組む機会に巡り合えたおかげである。
これら補職経験を、今回の森田室長の講話内容に照らしてみると、私は戦略を「戦いの謀りごと」として十分に認識した上で、その時々の戦略策定任務に携わっていたかというと少々自信がない。相手の各種情勢及び脅威の分析を重視していたはずだが、意図よりもやはり能力・戦力といった物理的なことに目が向き過ぎていたように思えてくる。
今日、各種の戦略策定にかかわる現役諸官には、この点を十分留意されることを望みたい。
CSC入校中に、瀬島龍三氏(陸士44期、戦後伊藤忠商事に入社し政財界で活躍)の講演内容についての資料を、知人から入手したことがあった。その中にも、やはり『戦略とは謀り事である』というフレーズが強烈な印象として残っている。前大戦において智略をもって立ち向かった軍人による最大の教訓と言えるのではないだろうか。
謀略、策略と言い換えてしまうと異なったニュアンスになってしまうかもしれないが、「相手が予期しない手段・方策を周到に準備し、確実に相手の意図を打破する。これにより相手の能力・戦力を減ずるとともに、味方の増勢を図る」という意味での、したたかな戦略が今の時代にも必須である。
そのためにも、昨今注目されているネットアセスメント(参考文献:「ネットアセスメントの再考:航空幕僚監部防衛部 1等空佐 坂田靖弘」)に関する取り組みと体制の早期確立は急務である。
(参考:「戦略」について)
「戦略」の概念については多くの論があり、“戦略とはこういうものだ”と言い切れる定義付は、日本にはまだない。
しかしながら、「戦略」については、その言葉の使われ方として幾つかの意味を持っていることは容易に理解できる。
まず第1に、「死活的重要性を持つ」という意味、例えば“戦略物資”“戦略産業”“戦略的地域”などがこれにあたる。
次は、「大局に決定的影響を与える」という意味、これに該当すると思われる使い方は“戦略空軍”“戦略兵器”“戦略爆撃”等である。
第3は、「方針、指針」という意味での使われ方として、“経営戦略”“販売拡大戦略”などがあげられるであろう。この使われ方は軍事以外の分野が多い。
第4番目は、「目標達成のための手段、方策」という意味である。“国家戦略”“軍事戦略”“防衛戦略”等の「戦略」がこれにあたる。われわれが本校で学び、考えようとしているのは正にこの意味での戦略である。しかしながら、この場合でも二つの異なった場面があることを認識しておかなければならない。
つまり、「当該目標を達成するために、現在保有する諸力をどのように使うべきか。」という問題解決型戦略と「当該目標を達成するために、将来を見通して今からどのような手(方策、手段)を打つべきか。」という未来志向型戦略である。われわれの身近な例を見た場合、前者は「年度防衛及び警備計画」(作戦計画)を考える場合の戦略であり、後者は「防衛力整備計画」等を策定する際考えるべき戦略である。今回諸君に考えて貰う戦略は、もちろん後者である。