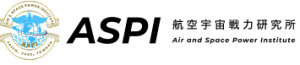Ⅰ 「昭和」からのメッセージ
1989年空幕が指揮官教育の充実施策の一環として編集した参考資料「言い残すべきこと」(―若き指揮官達のためにー)の中から、任意に抽出した指揮に関する題材(論題)の一つを記載。
1 はじめに
私は指揮所運用隊長を2年間、その後3年間の幕僚勤務の後、高射隊長を1年半の2回,編制単位部隊長を奉職しました。
この間は失敗の連続であり、今から考えると反省させられる事、残念に思う事等も多くありますが,本当に充実した3年半であり自衛隊生活の中で最も生甲斐を感じ、生気溢れ輝いていた時期だったと思います。
指揮行為は、指揮官の能力と人間性を合わせた全人格により実施するものであり、指揮官本人の能力又は人間性をカバーしたり拡大するテクニックは無いと考えます。
ただ指揮官も指揮を受ける者も人間であるため、相互の情報伝達の悪さに起因して部下が知らなかったり、誤解する事がありますが、指揮官の意図が部下に伝わらなかったり、間違って理解されたのでは.指揮は実行されません。
従って、指揮官は、常日頃から、人間性及び自分の考え、任務への取り組み方等を末端まで正確に伝えておくことが重要であり、特に、着任後日が浅く、これから部下に自分を理解してもらう立場の指揮官の場合は、若干のテクニック的要素をもって指揮を継続する必要がありますので、この点において指揮実行上のノウハウが存在すると考えます。
本課題に対して私は、これから編制単位部隊長に就く人の参考になればとの立場から、自分の経験した事で指揮実行上プラスに作用したと思われる項目を採り上げ、若干の説明を加えたいと思います。
2 指揮官としての心構え及び態度
指揮行為の主体である指揮官の生きざまは、指揮を受ける隊員の自主性,積極性を引き出す主要素であり,未熱であっても、真剣に努力しようとする指揮官の姿勢は、部下隊員の心に伝わり、進んで指揮下に入ろうとする部下の心情を醸成することになります。
指揮官が己を磨く方法は、各自が夫々真剣に取り組むべきことであり、ここにテクニックは通用しませんが、部下の立場から見て、重要であると思われる指揮官の心構え及び平素の態度は、次のとおりと考えます。
(1)自分の仕事に誇りを持ち,常に積極的であること
与えられた任務を正しく理解し,熱意と誇りをもって行動するとき、指揮官は生気溢れ、部下からみて輝いてみえます。
自己の責任を回避したり、困難を避けようとする態度は、すぐに部下に見抜かれ、真の服従を得られなくなります。 着任してすぐは、誰でも張り切っていますが、慣れるに従ってマンネリ化するのが通常です。初心を忘れずに自分の仕事の意義をみつめ、受け身に陥る事なく、常に債極的に、全力で努力する必要があります。
(2)部下に期待し続けること
指揮官だけでは何も出来ない事を認識し、部下隊員がその能力を最大限に発揮できるよう、部下に期待し、活躍の場を作ることに意を用いる必要があります。
専門的事項については、謙虚に部下の意見を聞き、部下に期待していることを示すように努めるべきです。古い知識や浅い知識で考え、専門意見を求めなかったり、知ったか振りをする等は厳に戒めなければなりません。
部下は、指揮官の期待に応えて自分の能力を発揮できることを最大の喜びとすることを認識するべきです。
時には、部下が期待に十分には応えてくれない事もあります。でも、指導の至らなかった事と反省し、少なくとも3回は部下に期待し続けることが必要だと思います。
(3)腹心を作らないこと
正しい状況判断は、広い分野からの正確な情報があって初めて可能です。有能な幕僚の存在は指揮実行上必要ではありますが、特定の部下に偏って重用し、腹心的に活動させることは、拓みを生じ、広く正しい情報が入らない環境を醸成することになります。
組織の機能に従って公平に部下を活用し、全部下が自由閥達に意見を言える場を維持するよう細心の注意を払うことが必要だと思います。
3 部下隊員の心情を知る
部下の実情とその心の動きを正しく知るのは最も困難なことであり、いくら努力しても限界があります。しかし、部下の心情は、完全には把握できないという認識のもと、それだけにー層、部下隊員の心情を知る努力を継読する必要があります。
部下の心情を少しでも正しく把握できれば,指揮の実行にあたり、部下の能力と特性に応じた施策と命令等の伝達か可能となり、その分、より適切な指揮が実行されることになります。
部下隊員の心情を知るための具体策として、次の事項が効果があると考えます。
(1)隊員カードを熟読すること
隊員カードは多くの人が記入しているので、局所にとらわれず総体的に見れば,かなり正しい個人の性向が記述されています。 余り先入観的にとらわれては幣害がありますが、隊員個人の人となりを把握するには、隊員カードを真剣に読んでみることが必要です。
(2)隊員と同じことを体験すること
隊員と全く同じ事を実施することは出来ませんが、出来るだけ部下隊員と同じ環境条件のもとに自分を置き、体でもって部下隊員の実情と心情を理解することに努める必要があります。
所詮、立場の違いや、日常的にやる事と、体験としてー時的にやる事の間には差異があり、完全には部下の心情は分りませんが、,部下隊員が何を喜び、何を苦痛と感じるかについての傾向は理解できるはずです。
激しい訓練も、リクレーションも、隊員と一緒になり体験することは、部下隊員の心情を理解するのに大きな助けとなるばかりでなく、隊員と指揮官の一体感の醸成に効果があります。
(3)私的な立場で共に遊び、共に飲むこと
公的立場だけでは、部下を知るうえで限界があります。仕事を離れて、部下とスボーツをしたり、囲碁、カード等の勝負事等を楽しむことは、指揮官と部下という職務上の壁を取り除き、部下隊員の本音を理解する上で効果があります。
階級意識を捨て、同じ仲間として、共に楽しく飲む場があるならば、なおー層深く相手を理解出来るでしょう。
しかしこの場合、交わる仲問が限定されると幣害があります。特定しない多くの隊員とフランクな気持で交わる機会を持つよう努めるべきだと思います。
(4)部下隊員との話し合いの場を設けること
指揮官が最大限の努力をしても、全隊員とつき合うことは不可能です。 性格的におとなしい人、内向的な人は、自分から進んで指揮官と接触することを避ける傾向があります。
こんな場合、隊員との話し合いの場を設ける必要があります。ある高射群司令は、隊員を10~15名ずつに分けて、お互いに体操服で話し合うという事を行われました。高射詳の全隊員と話し合うのは大変な時間と労力が必要ですが、ねばり強く実施された結果、隊員は非常に喜んで、本当の気持をぶつけている様子でした。群レベルでは隊員数が多すぎて大変ですが、編制単位部隊長がこのようにして全隊員の心情を聞くことは可能ですので、機会を作り、実行すべきだと思います。
4 相互の理解に努め、誤解を排除する
指揮官が自己を高め、部下の心情を理解した上で、任務に適合した指揮をしているつもりでも、立場の違いから、理解出来ないことや誤解が生じるのが通常であり、些細な行き違いが、指揮の実行を大きく阻害している場合があります。
指揮官は、これら指揮の実行を阻害する誤解等を生じさせないための処置を講じると共に、誤解がある場合は、これを解消する必要があります。
相互に相手を理解するのに効果があったと思われる方策は、次のとおりです。
(1)情報を共有し、目標の確認をすること
指揮官だけが情報を持ち、部下には多くを知らさないで指揮する方式は、旧式のやり方であり、現代青年を指揮するのに適する方式とは思えません。
部下に出来るだけ多くの情報を与え、指揮官と部下が共通の情報を基に判断し、行動することが出来れば、最も効果的な指揮の実行が可能だと思います。
このため、会議等に上級空曹等を参加させ、出来るだけ末端の隊員まで情報が伝わるように配慮するべきです。情報を共有し、その上で自由に意見を言わせることが出来れば、より効果があります。
年度の初めには、関係者全員を集めて業務予定表を作成するとか、毎月の訓練行事調整会議等あらゆる磯会に、可能な限り多くの部下隊員を出席させ、目標を共通の場で確認することは、相互理解に非常に効果があります。
(2)重要事項の決定の前に多くの者の意見を聴取すること
重要事項を決定する時は、指揮官としての腹案ができている場合においても、多くの部下の意見を聞く場を作るべきです。
戦国時代の武将が重要事項の決定に当たり、配下の武将を集めて意見を闘わせ、それを聴取した方式は、日本人の合意形成に適しているのでしょう。
この意見を闘わせる場は、部下の教育の場でもあり、十分に討議させ、それを聴取して自分の決定事項を藤認することが必要です。自分の思いもしなかった意見がでてくることがあり、指揮をより良いものとする上で非常に参考となります。
(3)訓練実施において工夫すること
部隊では訓練を苦しいものときめつけ、旧態依然のやり方で何の工夫もなく非効率に実施していることがあります。
確かに苦さに耐える事が訓練の主目的のこともありますが、訓練は十分に検討して、最も効果的に実施する工夫が必要です。
時には訓練の中に楽しみの要素を取り入れたり、豊臣秀吉の割普請の例のごとく競争させ、勝った者に賞を与える等人間の本性を活用したやり方を工夫すべきだと思います。
又苦しい訓諌をする場合は、その意義をよく末端隊員まで説明して、理解させた上で実施する着意が重要だと考えます。
5 むすび
指揮の実行の習得に王道はありません。幹部たる者、指揮官にたることを念頭において、常に修養に努めるとともに、未熟のまま指揮官なった場合は、指揮の尊厳を思い全身全霊で努力し、苦労しながら体得してゆくべきものだと思います。
あらゆる方法で情報が入ってくる現代においては、情報を指揮官が独占したり、判断根拠を伏せたまま、とにかく俺についてこい式の指揮は、余程の人格者か、常に正しい判断の出来る超人でないと、組織の総力を目標に向け結集することは困難です。
現代においては,むしろ自分の長所も短所もさらけ出し、部下と共に悩み、同じ土俵で考える指揮官の方が、部下の心からの支援を受けることができ、組識の総合力を発揮出来るのではないかと思います。
至短時間の判断と、組織的行動の要求される航空自衛隊においては、指揮官は、常日頃から部下とのコミニケーションを良くして、情報を共有し、一体となって活動出来る部隊を育て上げる必要があると考えます。
ここに挙げたことは、その様な考えで部隊を指揮した時の経験から引き出した所見であり、参考にはなると確信していますが、実際の場に適用するには、各指揮官の個性、部下の状況及び与えられた環境に適合するよう、独自の方法を工夫する必要があると思います。
Ⅱ 「平成」からのコメント等:
ここではⅠ項の大項目及びその内容を受けて、私が現役時代に思考及び実行した体験談を付言するとともに、関連しそうな当該ホームページ内記事をリンクとして掲載するもの。なお、以下の文中、「先人」とあるのは、Ⅰ項の論者を指している。
1 『はじめに』
私が「先人」と同じ高射特技者であるからか、ここでの論述の一文一文に親近感を抱き、2・3尉の初級幹部時代を懐かしむことができた。『特技愛』とでも言うのだろうか。この方と同一部隊で勤務していたかのような気になったぐらいである。
全国に展開する様々な部隊においては、それぞれ伝統や気風が異なる。その一方で同一任務を付与されている部隊同士には共通する文化のようなものが存在する。
これに関連して、同一特技者の間には初顔合わせの場合でも相互認識の心情が働くのは、日々の業務及び各種訓練にあって多くの共通項を体験していることによるのかもしれない。
編単隊長の就任期間について、「自衛隊生活の中で最も生きがいを感じ、生気溢れ輝いていた時期」であったと「先人」は表現している。私も定年退職となった今、36年間の現役時代を振り返ってみて「先人」の想いと全く同じである。
それは、編単隊の人員規模が部下一人ひとりを把握して指揮するにあたり多からず少なからず適当であり、活気ある現場の中心に位置して自らの命令・指示によって部隊を目指す方向に牽引できる醍醐味があるからではないだろうか。
私の編単隊長時代の感懐については、このホームページ内にある『勤務の思い出-「八雲分屯基地時代の思い出」』を読んでいただけるとその当時の雰囲気が伝わるのではないだろうか。若き指揮官である貴方には、ぜひ編単隊長職に就く前に読むことを薦めたい。
ちなみに、私の編単隊長職への思い入れの強さは、隊長職を離任する際に、隊員から贈られた時計付きの写真(縦30㌢×横20㌢)を自宅の机の前に飾り続けたほどである。今でも迷彩乙武装・ライナーに拳銃携帯、左手に指揮棒を持つ写真を目の前に置いている。
この『はじめに』の部分では、「先人」は指揮の実行にあたって情報伝達の不具合について記述している。もう20年以上も前になるだろう、情報は人を介すると多かれ少なかれ『歪む』という内容の記事を一般誌で読んだ記憶がある。(この記事に関しては、別の機会に紹介することとしたい。)
では、こうした情報の伝達不足、誤認及び誤解といった『歪み』を生じさせないためには、どうすべきか。私は朝礼、訓辞、講話等の様々な機会を作為、利用した上で、さらに文章にして関係部署に回覧する方法をとった。このメッセージ伝達の活用については、先月の『先人の知恵と経験(その2)』にて記述している。
加えて大事なことは、繰り返すこと、定期的に行うことである。この点で具体例を2つ示す。どちらも航空総隊司令官職にあった当時に、自ら作成し司令部内及び関係する部隊等に配布したものである。
一つは、指揮官職を経験した貴方ならば、作成した経験がある「年頭の辞」である。これ自体は、誰もが知るスタンダードな伝達方法の一種。もう一つは、その半年後に作成した「年半ばの辞」。これは、「年頭の辞」で示した部隊の目標とそれを達成するための具体的事項を、今一度総隊に所属する全隊員及び家族に知らしめるために配布した『繰り返し伝達』であった。
この2つの内容は別として、指揮官としての自らの指導方針及び部隊発展の方向性、そのために為すべき事項を部下部隊に対して誤解なく伝達するための手段の一つとして、貴方の指揮にあたっての参考になれば幸甚である。
************************************
年頭の辞
明けましておめでとう。平成28年の初春を迎えるにあたり、航空総隊(以下、「総隊」)司令部勤務の隊員諸官、そしで家族におかれては、それぞれの新たな展望とその実現のための決意を胸に、新年を迎えられたこととお慶び申し上げる次第。
司令部所属の隊員諸官においては、就任の辞で述べたように「変化への適応」「矜持の保持」「改善と自律の追求」の3つの統率方針の下、総隊の組織力を結集させる要となり、いかなる環境の変化にも、いかなる事態の発生にも適応するとともに、隷下部隊を精強かつ健全な方向へ導くための円滑で効果的な司令部活動を念頭に、個々の職務に精励することを引き続き強く要望する。
昨年末、本職に就任した以降、幸いにして緊急・不測の各事態への実動を伴う対処はなく、初度報告受けによる状況掌握、並びにBMD及び領空侵犯措置等に関する所定事項の確認を行う等、前司令官の指導・指示を踏襲しつつ、本年度の業務青酒及び練成訓練計画に沿った業務の推進及び任務の遂行を図ることができた1か月であった。
こうした状況の中にあって、「航空総隊の将来展望」(仮称)の作成を指示。総隊隷下部隊等の将来進むべき方向性を明らかにするために、司令部所属隊員一人ひとりの与えられた職務に対する真塾な態度はもとより、部課を超えた横断的な協力、そして隊員の業務遂行に対する家族の理解及び精神的支えを得ながら、早期に完整させることを心待ちにしている。
さて、今年は年度業務計画及び恒常的業務に加え、次の5項目を大きな目標とし、その達成のために全力を投じていくこととする。
第1に、就任の辞をもって自らに課した、航空総隊全体の隊務運営上の明確な中長期的なビジョンである「航空総隊の将来展望」(仮称)については、先述のとおり司令部各部署による協力のもと、年度末までに通達化を図る。今後は、司令部全隊員が総隊の将来像を共通の認識とした上で、各部課等と協力しつつ、課題解決に当たること。
第2に、年間の主要事業等については、以下の3つを特に重視する。
まずは、戦闘機部隊の体制移行において、対象となる飛行隊の人員・装備の移動を安全に完了させるとともに、移行前後における安定した隊務運営状況についても注視すること。
次に、伊勢志摩サミットに対する支援活動においては、他省庁及び他自衛隊と密接に連携しながら、遺漏なきよう尽力し国際的な国家行事に最大貢献を果たすこと。
3点目は、KE、CNG及びRFAをはじめとする各種演習のみならず、本年2月下旬に予定されている航空自衛隊図上演習に参加するにあたり、事前検討会をはじめとする諸準備に万全を期すこと。
第3に、日米防衛協力の深化という観点では、第5空軍司令部をはじめ米軍関係部隊との交流を演習訓練の内外を問わず積極的に実施する。このため、司令部は第5空軍及びPACAFとの各種調整においては、先行的かつ計画的に実施すること。
特に、共同の演習及び訓練については、これまでの実績をもとに体系の検討見直しに配慮すること。
また、米国以外のオーストラリアをはじめとする関係国空軍種との部隊間交流の方向性について、空幕等と協議を踏まえ、必要事項を明らかにすること。
第4に、総隊が保有する全ての装備品の可動率について、現状把握、原因分析、対応の方向性、具体的改善策に関する措置を明らかにし、部隊側の要求・期待に積極的に応ずる。
この際、単なる予算措置に依存するのではなく、業務改善活動を活用する中で、より質の高い維持整備にかかる各種態勢について見直し・検討を図ること。
また、QCサークル TPM活動(全員参加型QCサークル)の促進を図るとともに、防衛生産技術基盤の維持・強化のため関連企業との積極的な対話・交流を行うこと。
第5に、人的戦カの質的向上という点では、司令部所属隊員相互の団結と士気の高揚を図るとともに、メンタルヘルスを含む健康管理、レジリエンス力の強化、隊員を支える家族への支援等、人事・厚生面の施策を推進する。
このうち、すでに検討及び実施の指示済みである計画休暇については、早期に制度に準じて実施すること。
結びに、今年も総隊隷下の全部隊等における飛行及び地上の各安全を祈願しつつ、隊員諸官並びに家族の益々の健勝及び多幸を、加えて「Shift & Create to Grow」(変革と創造、そして成長)を合言葉に総隊の飛躍の年となることを祈念し、年頭の辞とする。
平成28年1月1日
************************************
年半ばの辞
航空総隊(以下、「総隊」)司令部勤務の隊員諸官、そして御家族におかれては、それぞれの新たな展望とその実現のための決意を胸に平成28年初春を迎えてから早半年が経過。
年明けから間もなく、日米共同統合演習の終了を待たずして始まった事態対応にあたっては、適切な措置を講じ、任務を完遂。その後も、各種演習を通じて指揮所能力の向上に努めるとともに、先述の同種事案、熊本震災、伊勢志摩サミット支援等、様々な事態対応に臨み、その都度、所定あるいは所望の成果を得てきたところ。まさに総隊司令部勤務者が一丸となって、直轄及び関連部隊を先導、牽引してきた結果であり、諸官一人一人の業績を心から称賛するものである。
こうした順調な隊務運営を行えている現下の状況にあっても、司令部所属の隊員諸官においては、就任の辞で述べたように「変化への適応」「矜持の保持」「改善と自律の追求」の3つの統率方針の下、総隊の組織カを結集させる要となり、いかなる環境の変化にも、いかなる事態の発生にも適応するとともに、隷下部隊を精強かつ健全な方向へ導くための円滑で効果的な司令部活動を念頭に、個々の職務に精励することを引き続き強く要望する。
さて、本年の下半期については、年度業務計画及び恒常的業務の推進に加え、次の5項目を大きな目標とし、その達成のために全力を投じていくこととする。
第1に、航空総隊全体の隊務運営上の明確な中長期的なビジョンである「航空総隊の将来展望」については、防衛部が主体となり、かつ司令部各部署による協力のもと、3月18日付で通達化。同通達については、1/四半期末をもって状況の変化を踏まえた見直し作業を実施し、第2版を作成したところ。あらためて司令部全隊員が総隊の組織理念及び将来像を共通の認識とした上で、各部課等が協力しつつ、各種課題の解決を図りビジョンの具現化にまい進することを切望する。
第2に、戦闘機部隊の体制移行を引き続き重視する。今後は、8,305、301の各飛行隊の人員・装備の移動を安全に完了させるとともに、体制移行の前後における安定した隊務運営状況についても注視する。
また、F35Aの導入に関連する事項として、操縦者及び整備員の米国委託教育を計画どおりに実施中。関連施設整備の進捗状況についても把握し、導入に伴う諸準備に万全を期す。
第3に、日米防衛協力の深化という観点では、第5空軍司令部をはじめ米軍関係部隊との交流を演習訓練の内外を問わず積極的に実施する。
特に、11月予定の日米共同統合演習については、将来の戦闘様相を踏まえた内容であることから、事前準備の段階から密接な調整に努める。
また、秋期には英空軍との共同訓練実施の計画が進行中。航空自衛隊史に残る成果及び今後の同空重との継続訓練を期待することから、空幕をはじめとする関係部署と密接な連携を図る。
第4に、総隊が保有する全ての装備品の可動率向上について、関係部署と連携し、具体的改善策を継続するとともに、F-35Aの導入に際して、運用に支障を来さぬよう必要な資格取得及び要員養成等の態勢整備を推進する。
また、昨今の品質管理上の不具合事案における教訓にかんがみ、過去のQCサークル大会において頭著な成果を収めた部隊による「QCサークル・サミット」を開催し、意見交換による改善策の反映をもって人的過誤の再発防止に万全を期す。
第5に、人的戦力の質的向上という点では、「意識改革」を念頭に置き、隊員に対するメンタルヘルスを含む健康管理、レジリエンスの強化等、関連施策の浸透を図る。
また、心身のリフレッシュを目的とした計画休暇の足着化、ワークライフバランスの推進により、介護、育児等と本来業務の両立に努め、隊員が高い士気と生き甲斐を持ち得るよう人事・厚生面の施策に積極的に取り組む。
結びにあたり、下半期も、総隊隷下の全部隊等における飛行及び地上の各安全を祈願しつつ、隊員諸官並びに家族の益々の健勝及び多幸を、加えて「Shift & Create to Grow」(変革と創造、そして成長)を合言葉に、総隊のさらなる飛躍を祈念し、年半ばの辞とする。
平成28年7月14日
************************************
2 『指揮官としての心構え及び態度』
「先人」の論文の小見出しにある「自分の仕事に誇りを持ち、常に積極的であること」をはっきりと自覚したのは、2等空尉に成り立ての時。
任期満了で退職する空士長からの深夜の電話が、准曹士隊員に対する平素の心がけや指揮官としての勤務姿勢はこうあるべきだと、私に意識付けた。
私は術科学校での教育を終え、関東に所在する高射隊に赴任。上司・同僚に恵まれ、年間の半分は、長距離走及び銃剣道の監督兼ねて選手としての競技活動を、残りの半年は高射隊特有の米国における年次射撃訓練のための練成訓練に明け暮れていた。
そうした中でも、服務指導の係幹部であったため、営内に居住する若い空曹士隊員としばしば接する機会があった。
彼らは年齢的にほぼ同年代、仕事自体の知識や経験は私より勤務年数が長い分、彼らの方が豊富である。特技関連の技能については彼らから学ぶことが多かった。時には下宿点検と称して、分屯基地周辺に間借りしている彼らにとって唯一のプライベートな空間を訪問していた。
こうして公私の付き合いを重ねていく中で、日々の仕事ぶりと年次射撃訓練での実績を彼らが認めてくれたのか、人事権を有しない付幹部の私に対する態度が変わっていくことに気づいた。階級に応じた服従の姿勢を感じられるようになった。
それから数か月が経過。私より年長で仕事もしっかりできる空士長が深夜官舎で就寝していた私に電話してきた。当時は、携帯電話は存在しないので公衆電話からだったと思う。
電話の内容は『付(当時、小隊長職に就いていない、若手幹部は「づき」は呼ばれていた)は、俺たち空士を信頼して付き合ってくれた。これからも俺たちのことをよく考えてくれ。頼んだからな』という主旨だったと記憶している。
その電話が私に対する激励、要望のいずれであったのか、また電話を受けた日については、すでに彼が任期満了で退職した後であったのかは、よく覚えていない。それでも若い隊員の心情に触れる機会を作ることの大切さを、彼の電話によってはっきりと自覚できた。
部下は常に指揮官の何気ない会話や動作をしっかり見ている。一つでも彼らに対する指導内容と相反したり、矛盾する行為を行えば、指揮は成立しないことを知らされたわけである。
とりわけ営内居住の若い空曹空士を常に関心の視野に置き、機会があれば懇談の場を設け、わずかな時間であっても本音の話を交わすことを強く意識するようになった。私なりの指揮統御の原点だと確信している。
3 『部下隊員の心情を知る』
ここでは、「先人」による論文の二つの中項目に関する内容についてコメントする。
一つ目は、「(2)隊員と同じことを体験する」。
前項に続き尉官時代の高射隊勤務における私の経験。部下一人ひとりが担っている任務とその達成に伴う彼らの行動を知ることが、いかに大事であるかをまさに身をもって体験した。
昭和50年代後半、空自が保有するナイキ・システムは老朽化して新機種への器材換装が求められていた時代。それでも年次射撃訓練(米国ニューメキシコ州においてナイキ・ミサイルの組立から実弾をもって実目標を迎撃する訓練等までの一連の訓練)は事業として継続され、高い成果を目指し相変わらず厳しい国内訓練が計画されていた。
米国年次射撃訓練に初めて参加したのは、ミサイル組立幹部兼ねて発射小隊長としてであった。当時の階級は3等空尉だった。
ある日の国内でのミサイル組立訓練に、クルーの一人(空士)が風邪で欠員となる事態が発生した。状況としては各人の練度を上げなければならない重要な時期に差し掛かっていたため、訓練は実施することとなった。
組立クルーは6~7名(記憶が少々曖昧)で、幹部1名が安全係として立会し、実際の作業に手を出してはならないと規定されていた。
この状況で欠員が担任する作業を代行者が模擬することで進めようとしたが、クルー連携の練成に効果的でないことにすぐさま気付く。
この細部状況を少し説明する。ミサイル組立に必要な重量物を上げ下げする行程があり、その際には、「Aフレーム」という簡易な手動式クレーンを使用する。この機材を主に操作する隊員が病欠となった。
そこで、当該作業を私が代行することになった。この場合、安全幹部が不在となるため、訓練効果を確かめる時間計測を安全重視の点から行わなかったのは言うまでもない。
「Aフレーム」の鉄製チェーンを作動させることは、私にとって初めての体験。うまくいかない、いくはずがない。重量物の上下動という点では問題はないのだが、要領を得ないため時間がかかって仕方ないのである。
この経験から、部下隊員の連携動作を把握できているとの私の自信は、多分に思い込みに過ぎないことがわかった。彼ら(当時は女性自衛官の任用制度はなし)がどのようにして作業に習熟したのか、コツは何なのか、その際の彼らの意識はどこにあるのか等を知ることが、指揮官にとっていかに大事かと痛感した。
以来、部下隊員が行う作業をOJTの一環として実務の妨げにならない範囲で実体験することにした。
その後、10年が経過して高射隊長職に就き、尉官時代と同様に部下が行う器材操作手順等に関して体験学習の場を求めていたところ、さすがに上級空曹から「そうした積極的な姿勢は理解できますが、隊長と一緒にシフト勤務に就くクルー員がことのほか緊張するので、やめていただけますか」と丁重に釘を刺された。
貴方も部下隊員と同じことを体験しようとする場合には、周囲に与える影響をよく考えること、実行する際には限度をわきまえることの着意を忘れずに。
もう一つは、「(4)部下隊員との話し合いの場を設けること」に関する事。
組織におけるコミュニケーションの重要性は貴方も知ってのとおり。問題は、そのやり様である。
公的な場では、会議形態や個人面接等の方法がある。課業時間内のしっかりしたコミュニケーションは極めて重要である。このことを踏まえつつ、私は高射隊長になった時から、半フォーマルなコミュニケーションを実践することにした。
どうしても指揮官と部下の間では、互いに階級、権限等を意識することになり、忌憚のない会話にならない。そこで、半フォーマルな会話力が重要になるわけである。
ちなみに、「半フォーマルな会話」について説明すると、自衛隊という戦う集団にあって命令と服従、階級の上下等という基本的関係を保った上で、相手に対する尊敬、期待、激励、思いやり、労り、気配り等、様々な心情を込めるコミュニケーション・スキルだと考えてもらいたい。
具体例として、ここでは2つの例を紹介する。
一つは、県人会の開催。
これは、貴方も入隊した以降、所属する部隊や入校する学校機関等においても経験があると思う。県人会、高校人会、地元会、いわゆる郷土を中心とした地域枠組みの関係は格別である。そこには共通の話題が山ほどあるはずだ。年齢差や性別があったとしても、話題は尽きないものである。
貴方もきっと基地の内外で郷里に縁ある同僚とこうした懇親の場に参加したことがあるだろう。私も異動のたびに所属部隊等において、長崎県人会を企画、開催して、忘れかけた片言の方言で会話するのが楽しみだった。
もう一つは准曹士隊員とのコミュニケーションの場。
前回(「先人の知恵と経験(その2)」、営内者の若い隊員との基地内夕食会(BBQ)を紹介したが、隊員食堂における昼食の場も大いに活用した。千歳基地勤務時代は所在部隊長との会食を、春日基地勤務の時代には同基地所在のすべての准曹士先任との合同昼食会を催し、転出入者や部隊毎のイベント結果の発表紹介を通じて互いの信頼感を深めた。
こうした平素からの何気ないコミュニケーションの真価は、基地及び分屯基地内で緊急事態が発生した時にこそ、大いに発揮されるのだと今でも信じている。
なお、「部下隊員との話し合いの場を設ける」の題材に関係ある、同ホームページ内のブログを一読いただけると幸いである。
1.春日基地勤務時代の思い出 「司令部勤務者を対象に長崎県人会を開催」 2.春日基地勤務時代の思い出 「准曹士先任との会食」
4 『相互の理解に努め、誤解を排除する』
ここでは、「先人」が記述する「(3)訓練実施において工夫すること」を選択してコメントする。
「先人」は個人及び部隊の各訓練のいずれにおいても、成果向上を目的として工夫が必要だと主張されている。そのとおりである。前例踏襲型の訓練ではマンネリ化に陥ることになる。
だからこそ、訓練規模の大小にかかわらず重点を絞り込み新味ある内容・要領を企画する工夫が必要となる。その際には、被訓練者又は部隊が状況下に入れるような設定に対する配慮も工夫の範疇であることを忘れてはならない。
私自身は、高射隊長時代にあって工夫を凝らす訓練の計画・実施に積極的に取り組んだ。当時、八雲分屯基地には3つの編単隊が所在していた。20及び23の両高射隊、そして後に改編となった第5移動警戒隊である。
私は第20高射隊長の職にあって、八雲分屯基地司令を兼ねていた。有事にあってはもちろんのこと、平時にあっても、特に災害派遣の事態においては、分屯基地所在部隊が一体となって任務行動をとることになる。
このために平素から所在の全ての部隊が密接に連携して災害派遣活動が整斉と行うことが求められる。
八雲分屯基地司令として、3隊合同の災害派遣を計画。当時は、当該訓練に様々な工夫を施すというよりは、前年度以前には合同訓練の機会が少なかったために、まずは合同対処訓練の実施に重きを置いた。
訓練の主眼、重視すべき訓練、相互の支援要領等を定めるにあたって、さほどの実績がないこともあって、各種検討を要した上に、所在3隊長の合意を取り付けるために関係幕僚は知恵を働かせることになった。
この続きとなる当該訓練の計画・実施状況等については、このホームページ内のブログ「八雲分屯基地勤務時代の思い出 「基地所在3個隊による合同災害派遣訓練を敢行」」を読んでいただきたい。
5 『むすび』
ここでは、指揮官が「自分の短所をさらけ出す」ことの是非について若干コメントしたい。
「先人」の論文中にある「指揮官は、常日頃から部下とのコミュニケーションを良くして、情報を共有し、一体となって活動できる部隊を育て上げる必要がある」との一文から、「先人」が指揮の実行にあたって、いかに部下との対話を重視していたかがうかがえる。目指す方向性はよく理解できる。私自身もこのスタイルを好む指揮官であった。
現代は、「先人」が勤務された時代よりもはるかに各種情報が氾濫し、その真偽を確かめることが極めて難しい。
指揮官が、断片的な情報、偏った情報等に振りまわされた上に、「先人」の言う『俺についてこい式の指揮』を実行するのでは、部隊の総力を任務達成に向けて集中させることは困難を極めるだろう。こうした状況に陥らないためには、部下との常なる良好な対話が重要となる。
一方、『自分の長所も短所もさらけ出し、部下と共に悩み、同じ土俵で考える指揮官の方が、部下の心からの支援を受けることができ、組織の総合力を発揮できるのではないか』との一文については、貴方はどのように考えるだろうか。
部下とのコミュニケーションがあってこそ、真の部隊戦力発揮に繋がるとの意図は明確である。ただし、貴方達の中には、指揮官が自ら『短所をさらけ出す』ことで、指揮実行上の不具合を誘発するリスクが生じるのではないかと大いに危惧する人もいるだろう。
私自身の解釈は次のとおり。
先の論文を拝読して、「先人」は空自教範「指揮運用綱要」に記述された『綱領』を学び、その原則を踏まえた指揮の実行に努められたと推察した。
中でも「指揮の本旨」にある『…部下に対し、もって部隊の模範としてその尊敬と信頼を受けるように努めなければならない』という点を特に重視されたと考える。
それは、「先人」は指揮官が職責を遂行するにあたっては、まず部下の心情把握を優先すべきとの一貫した論述から読み取れる。
この点から、『短所をさらけ出し』の内の『短所』を「人格形成にかかる欠点」と読み取るのは誤りであり、「不得意な事や他に見劣りする点」と読み替えるべきと考えた。
そうすると、貴方に質問した「先人」の一文は、指揮官は体裁にこだわらず、自然体で指揮の場に臨み、部下からのさらなる信頼を得ることになる一つの指揮のあり方であると言えるのではないだろうか。
『部下に見劣りする点をさらけ出す』という点では私も経験がある。
2度の北海道勤務にあって、ノルディック及びアルペンの両スキー競技はとても苦手であった。しかし、部下に訓練の実施を命ずる立場にあることと、当該競技会では指揮官率先が伝統であったことから、観念して部下隊員による厳しい指導の下、日々の練成に臨むこととした。
結果は貴方が想像するとおりである。千歳基地勤務のノルディック競技会の一幕をブログ化しているのでご笑覧いただきたい。
1.千歳基地勤務時代の思い出 「千歳基地ノルディックの試練」
2.千歳基地勤務時代の思い出 「またも来ましたノルディックのシーズンが…」
部下との良好なコミュニケーションにより、部隊の総意として隊務運営が整斉と行われることは指揮官にとって願ってもないことである。
しかし、情勢や状況の変化によっては、部下隊員の思いとは裏腹の方向に進む場合が生じる。むしろそうした結果になることが多いのは、不測・緊急の事態に対処することを任務とする自衛隊組織の特徴なのかもしれない。
指揮官は、部下に対して慈しむ気持ちを持つことを尊重すべきである。しかし、慈愛に徹するあまりに隊務運営にかかる判断を決して誤ってはならない。
したがって、指揮官は、部下とのコミュニケーションにあたって、慈愛と厳格の両面を兼ね備え、バランスのとれた表現・態度を示すことが重要である。
特に、任務遂行において難儀な事態に直面した場合には、一身上の心情にこだわらず、大所高所からあくまでも客観的に、そして合理的に判断することに専念すべきである。
また、指揮官が自ら下した判断・決心が苦渋のものであればあるほど、それに基づき部下に対して命令・指示を行う際には、指揮官のコミュニケーション能力の真価が問われることになる。