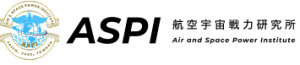幹部学校長の抱負『スマートパワーの源泉を目指して』(平成25年11月:尾上定正)
はじめに
8月22日付をもって第44代目の航空自衛隊幹部学校長を拝命しました。
本誌読者の多くが目黒基地の幹部普通課程等を履修された、もしくはこれからされると思います。私は、目黒基地での入校も勤務も経験がなく、このたび念願かなって、初めての目黒勤務となりました。
私が指揮幕僚課程を履修したのは、幹部学校がまだ市ケ谷基地に所在する時期であり、その後は米国への留学のため、高級課程等への入校は無かったからです。そのような経歴もあり、幹部学校で後輩幹部の教育や航空戦略の研究に自分の知見を活用したいと考えていました。
おりしも、幹部学校は来年、創設60周年、目黒移転後20周年の節目を迎えます。そのような時期に学校長に就任できたのも運命的なものを感じます。
本稿では、幹部学校について紹介しつつ、学校長としての抱負を述べたい
と思います。
学校長室の扁額「制空」
学校長室には写真の「制空」という立派な額【本額は、元内閣総理大臣 海軍大将 鈴木貫太郎氏が終戦直前の昭和20年8月4日、中央航空研究所(内閣の管理下、三鷹に所在)を視察された際、当時研究所長をされていた元海軍中将 花島孝ー氏の所望に応じ、進んで揮竃されたものである。なお、本額、その後花島氏が所蔵されたが、昭和38年2月本校の航空兵器課程の講師として来校された際、本校に寄贈されたものである】が掛けてあり、上記の説明がついています。学校棟2階のエレベーターホールには本額のレプリカが展示してあるので、ご覧になった人も多いと思います。
戦局を決定的に左右したミッドウェー作戦に言及するまでもなく、「空を制するものが戦を制する」という強い思いを、私はこの鈴木海軍大将の筆跡から感じます。
航空自衛隊の使命を突き詰めると、「制空」 の二文字になるのではないでしょうか。幹部学校に相応しい宝として、日々、使命の原点を見る思いでい
ます。
学校綱領
「制空」 の横にはかなり慎ましやかに、学校綱領が掲げられています。この綱領は、幹部学校の使命を踏まえて、学校職員及び学生が共通して目指すべき教育・研究の理念及び理念達成のための指針を明らかにする目的で、平成12年8月に決定されました。
その解説には、航空自衛隊の中・上級の指揮官・幕僚として必要な知識・技能を習得させるための教育訓練及び大部隊の運用等に関する調査研究を行うという幹部学校の使命(自衛隊法施行令第35条)を「航空戦略・戦術の教育・研究を極める」に集約し、「航空自衛隊の明日を拓く」で、学校の諸活動における叡智結集の方向性と将来に向けての決意を示した、とあります。
この理念を達成するための行動指針が、「明智、正義、勇気」です。防衛大学校出身幹部には、学生綱領の「廉恥、真勇、礼節」を想起させますが、簡潔な一文に幹部学校の使命が凝縮されていて、とても航空自衛隊らしいと私は思います。
「制空」という航空自衛隊の使命、「航空戦略・戦術の教育‘研究を極める」という幹部学校の使命は、極めて簡潔明瞭です。有事即応を旨とする航空自衛隊は、シンプルを美徳とします。デカルトの”A clear and distinct idea is true”の精神、あるいは、有名なDNA二重らせん構造の解明というノーベル賞論文がたった1ページである事実、また、「E=mC2」や「eiπ+1=0」に表現される真理などに共通する価値を、私はこの結晶化された使命に感じます。装飾を削ぎ落として本質を追究する精神と言い換えてもよいかもしれません。
私は、幹部学校に継承されるこの良き精神を基礎に、「航空自衛隊の明日を拓く」ための教育と研究を追求していきたいと考えています。
学校長勤務の土台
私は、1996年から2年間、ハーバード大学ケネディ大学院に留学させてもらいました。当時、「文明の衝突」という論文で世界的な論争を巻き起こしたサミュエル・ハンチントン教授、「決定の本質」というキューバ危機を分析した名著の著者グラハム・アリソン教授、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」 のエズラ・ボーゲル教授などの講義やセミナーを受講した記憶があります。
その時のディーン(学院長)が安全保障の専門家であり、ソフトパワー/スマートパワーの提唱者、ジョセフ・ナイ教授です。この留学時の水準の高い知的訓練によって、私の思考回路はかなり幅が広がり、論理的になったのではないかと思います。
私は、更に2001年から1年間、ワシントンDcの米国防大学NWCで学ばせてもらいました。アメリカの国家安全保障・軍事戦略を教育する最高学府の講義やセミナーは、非常に現実的かつ実務的でした。
特に、9・11同時多発テロが発生した後は、国防大学全体がシンクタンク化し、米国安全保障戦略の新たなパラダイム(枠組み)を、教官も学生も真剣に議論していました。この経験は、学術的な安全保障の理論を現実の政策や戦略に転換するための実務的な能力を高めてくれたと思います。
その後、航空幕僚監部防衛班長、人事計画課長、統合幕僚監部報道官、防衛計画部長等の幕僚職、第8航空団基地業務群司令、第2航空団司令の指揮官職等を経験し、ある程度「知識を能力に転化」 できたのではないかと思います。このような土台の上に、学校長という重責に臨んだところです。
学校長着任の辞:スマートパワーの源泉
着任にあたり、私は以下のような訓示をしました(抜粋)。
空自の中核となる指揮官・幕僚を育成し、かつ空自の任務遂行に必要な最適の部隊運用方策を案出し発信することが、学校長以下全職員に付与された責務である。
この責務を果たすため、私は、諸官一人一人に、それぞれの持ち場で、スマートパワーの源泉となって頂きたい。スマートパワーとは、部隊を戦略的に運用し、最も効果的に国益を確保するノウハウであり、我が国を取り巻く内外の現情勢を踏まえると、既存の枠組みにとらわれない柔軟な発想で、複雑かつ複合的な状況にいかに適切に対応できるか、即ち、どの程度のスマートパワーであるかが決定的に重要である。
(中略)私は、諸官とともに大いに議論し、学生の教育と調査研究を通じ、幹部学校をスマートパワーの源泉と成し、航空自衛隊の精強化に貢献したいと考えている。
我が国の安全保障環境は厳しく、自衛隊に求められる役割は拡大、多様化しています。尖閣諸島や北朝鮮の問題は、平時と危機の境界を暖昧にし、いわゆるグレーゾーンにおける政府全体の適切な対応が重要になっています。
また、技術の進歩は、無人機やサイバーなど今までに経験のない状況での対応を待ったなしで求めています。このような傾向は今後も継続し、一層深刻の度を増すと思います。
このような将来に備えるには、ナイ教授のいう「スマートパワー」 の強化が必要であると私は思います。
ナイ教授は、米国が冷戦後の複雑な国際関係においても大国であり続けるためには軍事力(ハードパワー)のみならず、理念や価値観・文化などのソフトパワーが重要であり、これらを適切に組み合わせたスマートパワーを行使する必要があると主張しました。
日本が直面する様々な課題を克服し、将来にわたって平和と繁栄を確保するためには、我が国もスマートパワーの強化が必要です。日本のソフトパワーは、先進民主主義諸国と共有する基本的な価値観に加え、東日本大震災で世界から称賛された国民性や魅力的な伝統と文化など、米国に勝るとも劣らないと思います。
ハードパワーたる自衛隊は、厳しい予算や定員の制約のため伸び悩み続けていますが、一流の装備と練度を備えており、今後の適切な防衛力整備によって、精強な存在としてその役割を果たすことは可能だと思います。
自衛隊のソフトパワー、例えば隊員の高いモラル(士気)や規律正しさ、部隊の即応態勢や統合運用などの無形の戦力も誇りにできるレベルです。我が国は、ハードパワーの行使に関しては、「専守防衛」や「集団的自衛権の不行使」等の政策によって、 一定の制限の範囲で行使するという選択をしています。
その補完として日米安全保障条約を締結していますが、「同盟国は助けてはくれるが、運命を共にしてはくれない」というド・ゴール将軍の警句も忘れてはなりません。日本としてどのような形のスマートパワーを目指すのか、今問われていると思います。
安倍総理の「スマートパワー」戦略?
本年9月の自衛隊高級幹部会同において安倍総理は、「現実を直視した、我が国の安全保障政策の立て直しを進め」、「国家安全保障会議を創設し」、「国家安全保障戦略を策定し」、「防衛計画の大綱も見直し」、「自衛隊の能力向上に取り組む」と訓示されました。
10月には、日米安全保障協議委員会(2プラス2)が開催され、「米国は日本政府のこのような取り組みを歓迎し」、「日米防衛協力の指針(ガイドライン)を来年末までに見直す」という共同声明を出しています。地球儀外交と称される積極的な外国訪問等と併せると、まさに日本のスマートパワーの戦略的行使と強化が進められていると私は思います。
航空自衛隊も、益々拡大・多様化する役割を適切に果たすため、統合運用を基本とする将来の戦い方や危機の拡大抑止の方策を研究し、体制を整え、教育訓練に精励し、任務を完遂できる部隊を育成しなければなりません。幹部学校はこのような方向に沿った研究と教育を実現する、すなわち、航空自衛隊のスマートパワーの源泉となるべしというのが私の抱負です。
幹部学校の現状と課題
幹部学校は、24年度実績で年間517名の学生を教育し、これまでに、延べ2万1千名を超える卒業生を送り出してきました。教育課程も時代とともに変遷し、現在は、幹部高級課程(AWC)、幹部特別課程(AOC)、指揮幕僚課程(CSC)、幹部普通課程(SOC)及び上級事務官等講習(CAC)の5コースを設定しています。
歴代学校長をはじめとする諸先輩方の努力で、教育内容も様々な改善が行われています。CS学生の国際感覚と英語力を磨くための多国間セミナーも、第13回目を実施し、大きな成果を挙げました。
部隊の中核となる幹部自衛官の教育は、「明智、正義、勇気」を柱とする全人格の陶冶と将来の航空自衛隊の任務完遂に必要な様々な能力の修得を目指さなければなりません。そのためには、「不易流行」 の理念を参考に、変えてはならない 「不易」と変えなければならない 「流行」を見極め、改善や改革を続けることが必要です。例えば、我々航空自衛官のバイブル的教範である「指揮運用綱要」は、昭和46年に制定以来一度も改正されていません。
その理由は、時代を超えた普遍性を持つ内容、即ち「不易」 の部分が大半を占める優れた教範であるからですが、一方、記述の前提を含め、大きく変化した環境や技術など「流行」を反映できていないことも事実です。学校長としては、学校綱領を自ら体現する覚悟で、学校職員とともに、時代の要請に適応した教育体制の構築を目指していきます。
幹部学校の使命のもうーつの柱である研究については、これまで「航空自衛隊のドクトリンに関する研究」などの成果を挙げてきました。航空自衛隊は、幹部学校の研究機能の質を高め、部隊運用により密着した研究成果を発信することを目標に、26年度、幹部学校研究部を航空研究センター(仮称)に新編する計画です。私は、先頭に立ってこの事業を推進したいと思います。
おわりに
創設60周年を迎える幹部学校の使命や課題について紹介しつつ、学校長としての抱負を述べてきました。拙文を参考に、これから入校される幹部は修学の志を立て、既に卒業された方は修学時の初心・所信を思い出して頂ければ幸いです。
また、教育や研究はどこで勤務していても、どのような立場の役職であっても、幹部自衛官として果たすべき役割だと思います。基地での幹部教育や自学研鎗の成果の「鵬友」への投稿など、自らのスマートパワーを高める努力を、全ての幹部に期待します。